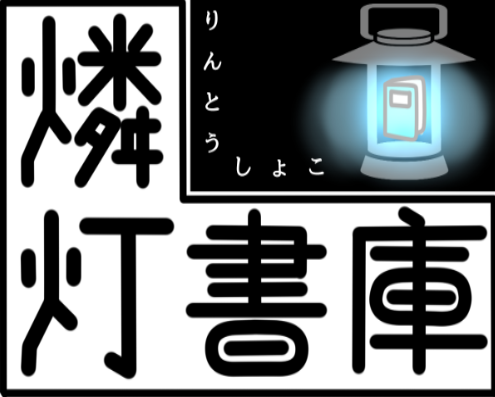踏み出すのは足、繋がるのは… 【後編】投稿日:2017-05-01 |
祭りの会場から離れても、商店街には紅白の提灯が並んでいる。
マコは田端と歩きながら、そこに書かれた店や会社の名前を、一つずつ眺めていった。
「どうして赤と白はめでたいのかしら」
「さあね……赤なんて、どう考えても血の色だよ」
「じゃあ、白は死に装束?」
「ああ、生と死か。日本人が好きそうだなぁ。……ふんどしにも赤と白が有るね」
「ふ、ふんどし……そうね、黄色や青はないもんねぇ」
錆びたシャッター。
雨漏りしそうなアーケード。
今日は祭りだからか、半数の店がシャッターを開けている。
横断歩道で立ち止まり、信号のボタンを押す。
田端は、バングルと一緒に手首に嵌めていたビーズのシュシュでふわふわした長い髪をまとめると、一息ついて呟いた。
「やっぱりちょっと休憩しない?例のカフェで」
「うん、いいよ」
歩行者用の信号を渡って、路地を入る。
古い住宅街。改築したらしい新しい家と、色がくすみ、ひびが入ったままの古い家が混在している。
路地は最後の十字路から歩行者専用の細い道になり、目的のカフェにたどり着く。
戦後に建てられたであろう平屋が丸ごとギャラリーカフェになっていて、古い門柱に質素な看板が掛かっている。
庭には池がある。
ふたりが近づくと、亀がのそのそ歩き出して、ぽちゃん、と池に沈んだ。
黄色いカタバミやハハコグサといった雑草が堂々と咲いている間から、優しいピンクのヒルガオが垣根に向かって伸びている。
ふたりは飛び石を渡って、古い木製の扉を開ける。
「こんにちは」
声をかける。暗い玄関の中を、裸電球が照らしている。
静かな廊下から衣擦れと足音が聞こえてきた。髪をふたつに結び、ゆったりとした生成の服を着た、マコより若干年長と思われる店主が現れる。
「こんにちは、いらっしゃいませ」
店主はひまわりのように、ふたりへ微笑んだ。
「いま、ギャラリーでガラスの器展をやってるんですよ……ごゆっくりどうぞ」
「ありがとう」
靴を下駄箱に仕舞いスリッパを履いて、古いけれどよく磨かれた廊下を進む。
重いガラスの引き戸を動かして、カフェスペースへ入る。
客のない5組の四人掛けテーブルが、15畳ほどの部屋に散在している。ふたりは窓際の席に向かい合って座った。
古い木枠の窓はガラスがところどころゆがんでいて、それを通して庭を眺める。
「俺が小さい頃育った家みたいなんだよねぇ」
「ああ……横浜の?」
「そう。池もあった。亀もいた」
「……玄米ご飯のランチあるよ、どうする?」
「ん……俺は軽くケーキでいいや」
マコはそれを聞いてもまだメニューを眺めていたが、やはりケーキセットに決めて、メニューを彼に手渡した。
大きな蜂が窓の外をうろうろと飛んでいる。
時折ガラスにぶつかり、こつん、と音を立てる。
マコが頬杖をついてそれを眺めていると、田端が店主を呼んだ。
ぱたんぱたんと足音が近づいてきて、
「……はぁい」
青いグラスをふたつ置いて、店の主人はゆるやかに微笑む。
「ええと、シフォンケーキを紅茶のセットでひとつ」
「私も同じ……だから、ふたつ」
田端がちらりとマコを見た。
注文を復唱して店主が去り、田端は置かれた水をひとくち飲みながら言った。
「珍しいね、コーヒーじゃないんだ」
「うん……たまには」
ふたりは黙って、同時に窓の外を見た。
細い松の木と、うっすら赤みがかった紅葉の木と、その下の二畳ほどの広さの池。
蓮の葉の合間に、小さな赤い金魚が泳いでいる。
亀の姿はまだ見えない。
池のほとりから水の上へ張り出している細い葉に、マコは何気なく目を止めた。
黒い蟻が先端へ向かって歩いている。
ふわっと風が吹いて、蟻は水面に堕ちた。
あ、と声が出そうになって、しかし出ずに、マコは田端の顔を見た。彼は気づいていない様子で、庭の木を眺めている。
蟻は手足を必死に動かして、水面を移動していた。
* * *
小さなベッドで、田端はマコを抱いた。
そこからしか、なにも始まらないと思ったからだ。白黒つかないことが、彼は嫌いだった。
薄暗い部屋ではあったが、下着を外したマコの肌には張りがなく、相応に年齢を重ねていることがわかって、田端は逆にほっとした。余りにも若くみずみずしい女は、ある程度距離を置いている場合には面白いのだが、こういう場になると萎える。
マコはキスの合間に乳首を軽くひっかかれる度、小さく吐息を漏らした。田端はずっと彼女の顔を眺めている。マコは彼のその表情に、好奇心以上のものを感じるような気がして、目を閉じる。
ーー勘違いはしたくない
彼の指先が両方の乳房の周りを丸くなぞり、鳥肌を立たせていく。やがて指先は下へ向かい、茂みの奥の、やわらかな裂け目にたどり着く。人差し指でくすぐるように触れ、その先を、ほんの少しだけ沈める。
「……久しぶりなの?」
「どうして」
「あんまり濡れないから」
彼女はゆっくりと目を開けて彼を見る。
「……緊張してるの……出会ったばかりの相手と、こうなるのなんて、初めてだし」
「そりゃそうだよね。彼氏は?」
「4年ぐらい、いない」
「へえ、意外」
田端は指で軽くそこをつつきながら、笑った。
「俺のこと、彼氏にしてくれる?」
「……いつもうまく行かないの、あなたともきっと、すぐにうまく行かなくなる」
「なにそれ、先月離婚した俺の話?」
彼はまた笑った。
「……ごめんなさい」
「冗談だよ」
田端に髪を撫でられて、マコはまた目を閉じる。
「案外うまく行くかもよ?うまく行かない同士なら」
なぜこんな必死に口説いているんだ、と田端は自身に苦笑する。
先月まで妻であった女と違う短い髪を指で梳いて、彼は、目の前の女との生活を想像してみた。まだ圧倒的に、情報量が不足していた。
しかし、一緒に生きるための大切なこと……たとえば歩幅のようなものが、妻であった女と目の前の女は違う、という直感があった。
「ねえ、このまま寝ちゃったら駄目かなあ?」
言いながら、彼は肘枕をしていた腕を、彼女の頭の下に伸ばして抱き寄せる。
「それであなたがいいのなら……無理矢理泊まってもらったんだから、私にそれを非難することはできないよ」
「ずいぶん堅苦しい言い回しをするのね、君は」
「……あなたは女の子みたいな言い回しをするんだね」
「俺、女の子の服のデザインやってるんだ……うちの業界では珍しくないのよ、こういうの」
彼が笑うと、マコの身体の緊張がひとつ、ほぐれる。
ーーおかしいな。こんな得体の知れない男に、ほっとするなんて。
* * *
マコは夢を見た。今までに何度か見た夢だった。
白い球体に閉じこめられている。体育座りしてやっとの大きさの白い球の中で、汗をかいている。
あちこち押してみるが、穴があかない。
重心を移動しようとすると球が転がっていってしまいそうで、彼女は動くのをあきらめる。
明日の仕事、どうしよう。そう思って、ため息をつく。今まではそこまでだった。
しかし今日は、新しい展開があった。
外からノックする音が聞こえる。でも相変わらず出口がわからない。
出たい気持ちと、出てはいけない気持ちが半々で、マコは迷いながらも出口を探す。
迷うから出られないのかもしれない、と思う。汗で身体がべとべとして、気持ち悪い……。
目が覚めて、身体を起こす。
心臓がどくどくと早鐘を打っていて、深呼吸をひとつする。
裸のままそっとベッドを抜け出す。
田端は少し頭を動かしただけで、起きなかったようだ。
玄関の横のドアを開けて、狭いユニットバスに足を踏みこむ。
トイレの奥のシャワーカーテンを開けて、湯船へ入る。
シャワーをひねると、冷たい水が出てきた。しばらくそれを頭からかぶっていると、だんだん温かくなって、そのうち湯になった。
それでもまだ、彼女は動けない。
ガチャ、と音がして、カーテンの隅から、田端が真剣な顔を覗かせた。
「おい!」
マコはびくりと身を竦める。
「え……?」
彼はマコを点検するように見て、ほっと息をつく。
「よかった、変な気でも起こしたかと思って」
「変な気って……ああ、手首を切るとか?」
「うん、そう。不安だとか言ってたから」
マコは微笑んだ。
「大丈夫……ごめんなさい、心配してもらって。あ……狭いけど、よかったら、一緒にシャワー浴びない?」
声をかけてから、男性と風呂に入るのは初めてだと気づいた。彼もまた、小さなその湯船を見て、
「え?……うん」
ためらいがちに答える。
マコが立ったままボディソープをスポンジにとって、自分の首周りを洗う。
田端は空の湯船に足を入れて、縁に腰掛けた。背中に張り付くビニールのシャワーカーテンを手で除けて、その模様を眺める。
黄色からオレンジ色にグラデーションがかかったアヒルの柄は、彼女という人から受ける印象とはずいぶん違うと思うと、自然に笑みがこぼれる。
「……夢を見たの」
「ふーん、良い夢?悪い夢?」
「わからない。汗はたくさんかいた」
「それでシャワーを?」
「そう」
彼女が自分の腕から胸を洗い終えると、田端は黙ってスポンジをとりあげた。マコの背中に、何度か握って泡立てたそれを滑らせる。
「……ありがとう」
「どういたしまして。どれもこれも下心だから」
マコは吹き出した。
「面白い人」
「そう? ふざけすぎて結婚指輪返上されるぐらいね」
田端はスポンジをマコに返した。
「……それだけで?」
「うーん、奥さんは真面目でしっかりした人だったんだ。俺の愛情がわからなくなったんだってさ。彼女は『愛情』がどんな形をしてるのか、知ってたんだな。俺にはまだわからない」
「……きっと相性が悪かったのよ」
私にもわからない……そう思いながら女友達への慰めのように言って、マコは彼の首周りをスポンジで洗い始める。耳の後ろから、肩へ、そして胸板へ。
「結婚生活って、想像がつかないわ。私、同棲もしたことないもん」
彼の背中に手を回して洗おうとすると、抱き合う格好になる。
「十人十色でしょ。同じ人間でも違うペアになれば、また違う結婚生活を一から始めるんだから……」
田端は手を伸ばして、シャワーの蛇口をひねった。湯が、彼女の泡を流していく。
マコが彼の手を引いて立たせると彼の泡も流れ、彼女の泡と一緒に排水口へ吸い込まれていく。
マコは田端の首に腕をまわして、口づけた。唇を舐めて、舌を呼び出して、絡めて、吸って、くちゅりと音を立てる。
皮膚がバリアを張っているようで、彼の手に撫でられるとそこへ電気が走る。
田端はマコの脚の間に手を差し入れて、裂け目を探る。今度は充分に濡れていた。その中にゆっくりと指を差し入れて、まとわりつく肉を熱く感じる。
「ん……」
田端は彼女のために、音を立てて舌を絡め続けた。
艶やかな声と息が漏れ、そのたびに彼女の肉は締まり、舌は濡れてさらに音を立てた。
マコは壁にもたれて、脚を湯船の縁にかける。彼の指を奥で感じたくて、彼女はあわせて身体を寄せる。
「いやらしいな……」
「……やめて」
「悪い意味じゃない」
「ん、あ……もっと……離れないで……」
マコはこれまで、こんな言葉の使い方をしたことはない。
小刻みに震える指を求め、彼女は目の前の男を信じて、思うままの言葉を口にした。
彼を求める言葉を紡ぐ彼女の声が、彼の指先を締め付ける肉が、今度は、田端の身体の芯をじりじりと焦がしていく。
シャワーでも消せない水音が、マコから遠いところで反響する。
瞬間、熱い波が身体の中心を焼きながら頭まで突き抜けていった。
悲鳴に近い声が漏れる。腰から胸に熱を満たして背中を反らす。息ができない。触れられていない乳首の先が、痺れて尖っているのがわかった。
頭の中が真っ白になって、やがて、ゆっくりと、視界と呼吸を取り戻す。
彼女の腰を支えていた田端の腕が、脱力した彼女を壁から引き戻す。
「もう、いっちゃったの?」
そんな簡単な言葉で片づけて、田端は今までマコの中に挿れていた指を、見せつけるように舐めた。
「……どんな味?」
興味本位で彼女は訊いてみた。田端は指を彼女の唇に突きつける。
「んやあ……」
顔を逸らし、拒む。田端がいたずらっぽく微笑んだ。
「混ざり合ったら、ひとつになれるかも」
「……なれないよ。ロマンチックな物言いは嫌いなの。……洗ってあげる」
愛情ではきっとない。しかし彼の好意になにかを返したいと思い、マコは彼の脚の間に手を伸ばす。
「ありがとう……」
今度は田端が目を閉じて声を漏らす。
そういったことに不慣れな彼女の愛撫だが、彼は身を委ねていた。
シーソーに乗っているようだ、とマコは思う。
相手と呼吸を合わせて、土を蹴り、着地する、それをただ繰り返すだけでよかったのに。
ーー私は今まで付き合ってきた男の人と、何に乗っていたんだろう
シャワーをマコの手から取り上げ、壁のフックに掛けて湯を止めると、田端が、かすれた声で問う。
「名前を」
瞬間、マコは目を伏せた。
「マイコ……舞う子って書くの。嫌いよ、この名前」
「ふうん……嫌いなの」
彼の右手が、マコの頬を撫でる。
彼女の右手は、彼の左手に導かれてそれを包む。びくん、と彼のものがマコの手の中で震え、ひときわ張りつめる。
「……でもどんな名前かは重要じゃない。どう呼ばれたいか、が大事」
「マコって呼んで。……あなたは?」
「田端コウスケ。右に立つ人と幸せになる、倖佑」
「コースケ」
田端は背を丸めて、口づける。
頬を両手で包み、今夜、何度もしたように、また舌を絡める。
何度もしたように、唇を食む。
田端は彼女の手に自分の手を重ね、動きを早めていった。それが、彼なりの誠実であった。
「……マコ」
彼女の首筋を舐め、耳に舌を差し入れ、彼女の吐息が漏れる度に、彼は名前を呟いた。
彼の息もまた荒くなり、マコは急にせつなくなって、彼に脚を絡めた。
田端は鼻の触れる距離で彼女を見つめ、
「次があるって、思ってもいい?」
訊く。
彼女は自分の太ももに、熱く固い彼のものをあてがって、その指で絞り上げる。
「私も訊きたかった」
欲情があふれるままに、マコは田端の唇を貪った。
舌を差し入れると、彼の粘膜は柔らかく温かで、マコは自分が受け入れられていることに感動する。
胸の奥の方から何か熱いものがこみあげてきて、彼女の目にじわりと溢れた。
田端は、自分には理由のわからないその涙を、そっと人差し指で拭う。頬を寄せて耳元で言った。
「次は……ちゃんとしよ……最後まで……」
マコが頷くと、添えられた田端の手の動きが速まって、
「ごめん、出すよ……」
かすれた声のあと、少し呻き、息を詰め、彼の精液がマコの太ももに飛んだ。
田端は彼女の肩に額をつけて、大きく息をつく。
マコは手にわずかについた白いそれを、バスルームの灯りに照らして眺めると、ほんの少しだけ、舐めてみた。
* * *
池の金魚は蟻に気づき、水面に口を開いて、食べようとした。
しかし、金魚はとても小さく、それほど空腹でなかったらしく執着もせず、蟻は命拾いをしたようだ。
水に垂れた草を伝い、陸へ上がって消えた。
「ねえ」
田端は、空いたケーキ皿の横にカップを置いて、まっすぐにマコを見た。
「なんで俺と結婚しようと思ったの。焦ったから?」
マコは、静かになった水面から目を離さない。
確かに、相手は誰でも良かったのかもしれない。
彼女はゆっくりと、心の中を探る。
「……それもある。でも、それだけじゃないよ」
あの夜に降っていた雨は、まだ時おりマコの中に降る。
冷たく激しい雨。あの夜の孤独と焦りを思い出す。
長年にわたる自分の不器用さに嫌気がさして、この先、いいことなんかないんじゃないかという不安に叫びたくなる。
しかし、田端はマコの雨にたびたび気づいてくれた。雨が上がるまで、他愛もない話をして笑ったり、触れ合ったり抱き合ったりできると教えてくれた。
田端が横に居てくれるおかげで、待つゆとりが生まれた。
無理する必要はない、気を紛らわせながら雨が上がるのを待てば良い、そう思うようになってからは、田端が隣にいない日も、雨宿りができるようになった。
あの日、土砂降りの闇に踏み出してなりふり構わず歩いたことを、間違いだと思っているわけではない。
もし必要なら、次はためらいなく踏み出すだろう。
たとえどんなに暗い闇の中へでも。
「コースケ、髪、伸びたよねえ……あんたはほんとに優しくて、たぶんいろんな意味で相性もよくて……」
背筋を伸ばして、正面から彼を見る。
ガラスがコツン、と音を立てた。また蜂がぶつかったのだろうと、マコは思う。
ふいにマコの目から涙がひと筋こぼれ、言葉が口をついて出た。
「ねえ、いつも、手を、繋いでいてくれる?」
田端は少し驚いて、それから、
「ああ、もちろん」
微笑んだ。
「馬鹿な話、沢山してくれる?」
「ああ、馬鹿な話をしてあげる」
「ずっと?」
「ずっとだ。お互いに理解しようと努力できるなら、俺はずっと君の横にいるよ」
「うん」
マコが鼻を啜りながら鞄からハンカチを出そうとすると、ふたりで記入した婚姻届が、ちらと見えた。
マコは腕時計を見る。
そろそろ行かなくてはいけない。
いくら、休日で役所の守衛に渡すだけだといっても、暗くなる前には済ませたい。
ハンカチを目頭に当てて、鞄の隅にまた戻す。
目の前のカップを手に取ると、最後のひと口を飲み干した。
「行こうか」
「行こう」
二人は同時に立ち上がると、顔を見合わせて笑った。
(終)(初出 2014-8)