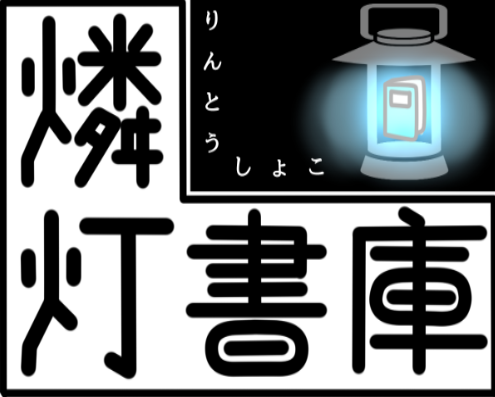タンデム・パラレル・センチメンタルな夜投稿日:2017-11-21 |  |
#1
アパートに帰って、もう一時間になる。
その間、エアコンはフル稼働して、私の部屋は熱帯から温帯にまで涼しくなった。
もうエアコンを止めて窓を開け、シルフの出入りを待っても良いのだけれど、動けずにいる。
仕事のスーツのままベッドにうつ伏せて、いつもなら帰宅してすぐ脱ぎ捨てるストッキングさえそのままで、私は、時折鳴る着信音だけに反応していた。
表示される雅也からのメールに、左手でだけ返事を打とうとして、でもやっぱり打ちにくくて、右手を伸ばして入力、左手は支えにする。
——さっきから同じこと繰り返してる、私
苦々しく奥歯を噛んで枕に顔を埋める。
*
『15分後に行くから、未生は屋根に上がって待ってて』
と着信。
音が鳴ると同時に顔を上げ、内容を確認してから、
『屋根に降りたらまた大家さんに叱られちゃうよ!』
と返信した。その、軽く責めるような口調の裏返しか、口元がにやける。
せーのっ、と掛け声をかけて私は起き上がった。
戦闘服のような仕事着を脱ぎ、半袖のTシャツと、薄手の長袖パーカー、スウェットパンツに身を包む。
パーカーのフードを被ると、ふうっと柔らかな気持ちになった。
いくつかの持ち物を小さなナップザックに入れ、くるりと背中に回して固定。
水を一杯飲む。玄関の鍵をかける。部屋の明かりはつけたまま、窓を開けた。
帰宅時より涼しくなった外気は、けれど部屋の空気よりもムッとして暑い。
「あ、クーラー……」
リモコンで電源を切り、部屋を見回す。玄関のスニーカーが目に留まり、取りに行く。
「うん、大丈夫かな」
一通り確認し終わると、窓枠に歩み寄って足をかけ、奥行き30センチほどの小さなバルコニーに靴を乗せてそれを履く。掴める場所をみつけ、うまく体重移動しながら、カーテンと窓を閉める。そして、雨どい伝いによいしょよいしょと屋根にあがる。
*
被っていたフードを外して、ショートカットの頭をブルブルと振る。
屋根の上は、部屋のあたりよりも少し、風が吹き抜けていた。明るい満月に、ちらほらと星も見える。
このアパートは二階建ての、単身者用ワンルーム。ここのあたりは蔵賀谷でも二、三階建ての建物ばかりが密集している地区だから、周囲は薄暗い。
ところどころ白い光が漏れているのは、たいていがコンビニの看板だ。
少し南に離れた繁華街には、ネオンサインが反射する色とりどりの古いビル。
その先、一段高く、ゆっくりと点滅している赤い灯は、香我美特区から時山駅前にかけた高層ビル群の屋上。
南の空、蠍座アンタレスは、それらの上にある。
「あっかいーめっだまのさそりー……」
私が帰る頃には、蠍がビルに飲み込まれてしまっているだろう。
「ひろーげたー鷲のつーばさー……」
ビルの遥か上をまっすぐに横切っていく、紅白の尾灯をもつ影が飛行機。
そしてビルのすぐ上を鷲のように滑空していく影がワイバーン。
「……オーリオンはたかーくうたいー」
ふいに、遠く背後で呼び笛が鳴った。
振り返って北の空を見る。
ーーーーーーーーーー
#2
未生(みお)は、ちゃんと暖かな恰好をしてくるだろうか。
夏といえども、夜間飛行に半袖Tシャツは若干涼しすぎた。もう一枚着てくれば……心の中で舌打ちするが、今更どうにもならない。もう一度、意識を目の前のワイバーンに傾けた。
身体の大きさは、だいたい軽自動車のワンボックスカーに頭と尾がついている、と言えば良いだろうか。
首から胸にかけては緑のゴワゴワした皮が、頭から背中にかけては深緑に光沢のある鱗が光っている。
広げてみせた臙脂色の翼は、よく伸びるトランポリンのようだ。その先に、尖った爪がついている。
翼を閉じながら、僕の頭がすっぽり入るほどの口を開けて軽く咆哮する。歯並びの良い、白く尖った牙は、特に威嚇をしているわけでもない。
鷲のような、しかし力強い脚は太い。
そして、特徴的な、白い魔法陣が胸に刻まれている。最近ワイドショーで嘆かれている“野良バーン”ではない、という印だ。
「半年ぶりぐらいだね、覚えてる?」
かれの首から胸元へハーネスをつけながら、僕は話しかけた。
かれは小さな金色の目で見つめてきたが、少し遠巻きに匂いを嗅ぐような仕草をして、また興味なさそうに視線を逸らした。
「忘れちゃったか……」
ここは蔵賀谷でも山寄りの、古いビルの屋上にあるサモンポートだ。大型乗用幻種のための、召喚ポイントである。下の階にハンドリングカフェという、いわば幻種レンタカーのような店があって、僕らはたまに利用している。
「大丈夫ですか、喚び直し一回までなら無料ですけど!」
高校生のようにも見える店員がスリッパをパタパタと引きずりながらやってきて、僕に言った。
「うん、かれは忘れているようだけど、相性は良かったはずだから……このままで」
「間が空いても、マナの相性はあまり変化しませんからねえ」
ウンウンと頷いた彼は、朝4時には特区と時山駅前の自由飛行時間が終了することを僕に確認すると、ワイバーンの首をポンポンと撫で、階下のカフェへ戻っていった。
ハーネスを軽く引いて最後の安全確認をし、合成皮革でできた安い鞍と、ベルトで自作したあぶみをセットする。
「さぁ、乗るよ」
伏せをさせたワイバーンによじ登る。
ふう、と軽く息を吐きだして、鞄から、ファイアドレイクの抜け皮で作った巾着を出す。そして、中に入っている薄緑色の方解石のかけらを掌に乗せる。
これは、僕が弟子入り志願している魔具職人のレプラコーン、ジェイド石川さんから分けてもらった、マナを増幅させて幻種の気を引くためのツールだ。
今度は、すう、と息を吸い込み、神経を集中させて、身体中のマナを集める。
テノールの高い声を出す時のように、掌へマナを送り出すイメージを持つのが、僕のやり方だ。
方解石から僕のマナが立ち上がる。
それは、初夏の樹々から漏れ来る光のような、深緑の輝きを放つ。
静かな声でシルフへ呼びかける。
《吹き征く者よ聞きし給え、我が示す先への導きを賜らん》
少し待ってみるが、応答がない。
今日は出払っているのかな、仕方ない、自分で手綱を握るか……と半分諦めたころ、目の前に、小さな、半透明のミルク色をしたオムニ・ファンタジアスのシルフが浮かび現れた。
「道案内ね、引き受けまショウ」
堅物そうなシルフだ、話を聞いてくれるかな、と一瞬僕は考えて、それを慌てて打ち消した。
かれらとのやりとりには、【開く】ことが不可欠なのだ。【閉じている】ことが相手に知れると、途端に姿や声が見えなくなってしまう。
僕はそのシルフのポニーテールがユラユラ揺れるのを眺めて、声をかける。
「忙しかった?来てくれてありがとう。ワイバーンで海までタンデムしたいんだけど」
「ここから海まで? ……あなたのマナは珍しい匂いがしますでショウ」
口元に手を当てながら僕の掌を覗き込む。
「そう、この時間混み合っている駅前を抜けたいんだ。その前に一人拾っていく。……気に入ったら、好きなだけどうぞ」
フフ、と微笑んで、僕の掌にそっと両手をかけると、口を寄せ、僕が方解石に集めたマナを飲み干した。
蝶みたいだ、と、僕はいつも思うのだ——昔、家族と行った熱帯植物園の蝶は、砂糖水を含ませた脱脂綿に群がってきた——今もまたそれを思い出した。
乳白色の羽や身体が、徐々に淡い緑色へ変わっていく。
「アア、もうお腹いっぱいで、ほんとうにごちそうさま。あなたスプリガンの家系?森のいい匂いがするでショウ」
「スプリガン?なるほどなあ。背が高いからジャイアントだろうっていうのはよく言われてきたけど」
「へエー。スプリガン系ヒトのマナは希少だけど腹持ちが良しと聞いたでス」
「はぁ、腹持ち……」
「シカシナガラ、どこかでもう一人拾うって話をしてたでス?」
「うん、えっとね」
かれがワイバーンの額に刻んでくれた印は、南風を乗りこなして進むルートだという。
「だから、寒くはないでショウ。さよなら」
「ありがとう、またどこかで会うことがあったらよろ」
言い終わる前に消えた。
オムニのそんなところがオムニだな、と苦笑いしながら僕はワイバーンの首にしがみついて身を乗り出し、かれの胸元に掌を当てる。
《古より天空の長たる飛竜よ、その翼もて我らを伴い給え、吹き征く者の導きのもとに》
ワイバーンは頷くように、あるいは祈るように、軽く頭を下げると足にバネを効かせ飛び立ち、二度三度羽ばたいて、ネオンサインと高層ビルの方角へ、風に乗った。
ーーーーーーーーーー
#3
呼び笛の主は雅也だ。
緑のワイバーンが、この屋根に向かって降下してきた。
私は振っていた両手を上へ伸ばし、そこで静止する。
ワイバーンがゆっくりと、傍を通過しようとしている。どこに降りるのか、と戸惑っていると、雅也がその背中から身を乗り出した。太めの革ベルトを私の両手に掛け、カウボーイよろしく自分の前に引き上げる。
「痛っ」
小さな声が出てしまう。
「ごめん、大丈夫?」
私は、ハーネスにしがみつくようにしてワイバーンの背中によじ登った。
半身後ろを向くと、困ったように眉毛を下げた顔。
思わず笑いながら、まくし立てる。
「あは、びっくりした!前みたいに屋根に止まると思ってたじゃん。まっさかそのまんま引き上げるなんて、あんた意外と力持ちだったのねえ!!でもこれなら大家さんに叱られない。ねえ雅也、このワイバーンて、私、前にも乗ったことある?」
左手でハーネスを握り、ゴツゴツとしたワイバーンの背骨に乗せたお尻を座りのいいように調整する。
雅也はベルトにくくりつけていたゴーグルのひとつを私に手渡して、回答した。
「前に、海へ行った時の」
「あーはいはい、そんな気がしましたー」
雅也は続けて、
「今日も、海でいいのか」
と聞いた。
私はゴーグルを装着して、頷く。
「うん、お願い」
蔵賀谷の低層地区とネオン街を抜けると、正面に高層ビル群が迫ってくる。
ブオン、と風切り音がして、ビルの、まだ明かりが灯る部屋へ白い腹を見せつけるように、ワイバーンは水平に翔けた。
「バランスとって、掴まって」
雅也は静かにそう告げると、私の両腕を外側から抱えるようにしてハーネスを掴んだ。
父のオートバイに乗せてもらったかすかな記憶が背中に蘇り、私はちらと振り向こうとして、
「ん?どうした」
耳のすぐそばに彼の声を聞く。
「ううん、なんでもない」
「重心低くしてね」
「はぁい」
ビル街を見まわすと、今夜は週末だからか、ハンドリングワイバーンの姿が多い。雅也はビルの合間を飛ばせるつもりなのだろう。
特区十二番街を左へ。道路の渋滞を下に見ながら、”マギアテクノ北”の交差点を右、舗道に並ぶ唐楓の少し上を翔ぶ。
右へ、左へ、私たちはワイバーンに身体を預けて重心を移動する。
「あ!その先を右へ行くと、私が働いてる製薬会社よ……」
昼間のオフィスでの喧騒を思い出すと、まるで嵐の舟に揺られているような、若干の眩暈とサイレンのような耳鳴り。
「ああ。18階だっけ」
「そう」
営業部は人種ー幻種間対立のひどい部署で、私の神経は消耗しきっている。
『所詮デミはデミだな。なんでも魔術で解決しようとする』
『それの何が悪い!科学なんぞ太刀打ち出来ないくせに!』
『なんだと!!』
昼間の会議を反芻する。
「嫌……」
雅也に聞こえないように呟くが、耳鳴りは治るどころか酷くなる。
目を閉じる。髪にかかる温かな息。
「相変わらずでかいビルだなあ……」
背中に響く低い声。風が耳を掠めて起こすホワイトノイズ。弾力のある翼がはためくたびに生まれる、微弱なバイブレーション。
——これは幻だ
耳鳴りの向こうで囁く声がする。
これが幻なら総てが幻ね、と私は応じる。
——現に生きよ
声が諭す。
——現って、どこにあるの
——……
——ねえ、どこにあるの
声の主は消えた。
なんにしても、空っぽの自分を、うっとりするほど甘く、狂おしく熱い、煌めきと切なさのマナで埋め尽くさなくてはいけない。
そうしてここのところ失ってしまった自分を、自分に取り戻すのだ。
——まだだ、まだ足りない。
私は向かい風に乱される髪を片手で押さえて、前を見据える。
*
ビルの切れ間を抜けた。
待ち構えるステーションビルと、波打つホームの屋根が5番線まで。それを越えた先に暗く沈んでいるコンテナの群れ。そして照明のなかに鎮座する、夜間発着の大型貨物船たち。
風の溜まりを越えるように、ふわっと線路を乗り越えてから、ワイバーンは少し高度を上げて気流に乗り、その翼を止めてグライダーさながら滑空した。
この暖かな風は、南風。
「海に出てどうするの」
雅也が言った。
「今日は満月よ、それに、満ち潮」
「ああ。前に遭遇したあのマーメイドたちに会いたいなら、灯台から磯の方へ回ってみるか」
「うん」
ーーーーーーーーーー
#4
僕は、ワイバーンと一緒に埠頭の小さな灯台の踊り場に腰掛けて、黒曜石を削っている。
シュッ、と最後のひと砥ぎをして、月の光に刃先を照らす。掲げた石刃で、月を透かして眺めると、月は、スモークがかかった黄色になって、わずかに歪んでいる。
さっきの騒ぎを思い出して、僕は軽く咳払いをした。
*
上空で滑空するワイバーンから、波間に人影が見えた。
『あ、いるいる』
未生はそう言うと、鼻歌交じりにパーカーとTシャツを脱ぎ始めた。
『なっ!?おい!!ここから飛び込むつもり?!』
『うん……これ、お願い』
さっさとスウェットまで脱ぐと、海面の影から目を離さずに僕の胸へ押し当てる。
『ちょっと待て!』
僕は目を逸らしたり逸らさなかったりしながら彼女の着替えとスニーカーまで受け取り、慌ててワイバーンのハーネスを強く引く。
急降下が始まり、水面すれすれのところで彼女はやっと僕の顔を覗き込んだ。
『じゃっ!』
ドボン、という音とともに、彼女は消えた。
『じゃっ!じゃねえよ……』
残された僕は一人ごちて、ワイバーンを上昇させるべくハンドリングしながら、あっ、と気づく。
『ゴーグル!!それ、水陸両用じゃないんだけどォ!!!』
叫んだが、寄ってきたマーメイドたちと、キャッキャと再会を喜んでいるらしい彼女の耳にはきっと入っていない。
僕の革バンドゴーグルは、かくして海水に浸されることになり、諦めてこの灯台に陣取ることにしたのである。
*
「水着かなあ、あれ」
歪んだ月を見上げながら、いや、どうみても下着だった、と思い直す。
「全く……もう……」
顔をゴシゴシとこすってため息をつく。
鞄から、石刃磨き用の革を取り出そうとして、何かが手に当たった。オペラグラスだ。取り出して、目に当てる。
水を打つ音と歓声の聞こえる方を覗いてみるが、月明かりにオペラグラスの狭い視野ではなかなか捕まらない。
と、不意に、初めて聴く、それでいて懐かしいハーモニーが小さな湾に響き、僕はオペラグラスを置く。
マーメイドは歌が上手だと言われている。
元々が水棲種族なので、絶対音感などとは別の、超音波に近い音域での独自の音感や音階を持っているのだと、数年前のNature誌で発表されていた。
前にここで彼女たちに会ったときに聞いた話によると、SNSで集まった、いわゆる合唱サークルの定例会なのだという。
『できるだけ幻界の歌を幻界で歌ってたように歌いたいの。だから、こうやって、こっそり夜中に定例会』
僕は夜空を見上げた。
「あいつの歌、かぁ……」
*
彼女自身、今年になってから知ったと言うのだが、マーメイドの血を引いているらしい。先月、DFT(Demi Fantajius Type)鑑定をして15%マーメイドだと確定したというのだから本物だ。
幼い頃の祖母の「海へ行ってはいけない」という言いつけを律儀に守っていた彼女は、海棲オムニと話ができるのも最近知ったという。
「陸のオムニとは話ができなかったから、中学生の時なんかオムニの授業が苦手でさ、先生に『真面目にやれ!』って怒られたりしたよー。たぶん血筋と関係があるんだよね。でもさ、海には行かないし、ヒレだって鰓だってついてないし、マーメイドだなんて気づくわけないじゃんねぇ」
*
静かになった海に、キャハハという笑い声と、バシャン、という音が聞こえて、
「……水着かなあ」
もう一度オペラグラスを覗く。
「……いや、下着だな。うん、下着だ。これはしかし色気も何もない」
目を離して、オペラグラスを鞄へ戻す。
そして入れ代わりに出した革で、石刃を磨くことにする。
となりでちょこんと座っていたワイバーンが、僕の方を見て、大きなあくびをした。
僕は石刃を磨くことに集中する。
ーーーーーーーーーー
#5
ひとしきり歌って、遊んだ。
マーメイドさんたちは
「そろそろ着替えないと終電来ちゃう!」
と慌てて陸へ帰っていった。
私はさよならをした海面でひとり、仰向けに浮いて、夜空を眺めている。
——このまま沈んでしまえたらいいのに
時おり、大きくなる波に顔を洗われた。
「んく……んはっ……」
そのたびに私は息を継ぎ、隙をついて流れ込むわずかな海水を味わう。
耳の中の水が、ちゃぷん、という波の音すら遠くに押しやって、静かな海には私の息遣いだけが生きている。
——ずっと、ここで
息を吐きながら胸の上で手を組む。浮力の均衡が破れ、海底に沈んでいく頭。
開いたままの目に映る月明かりは揺れて、溶けて、遠ざかる。
息遣いの代わりに響く鼓動。
酸素を求めて喘ぐ、絞られる肺。
——私に鰓ができるのと、死ぬのと、どっちが先かなあ……
酸素不足の頭でぼんやりと考え、目を閉じかけた、その時。
蒼く光る手が私の手を掴んだ。
ハッと目を開く。
微笑みながら顔を寄せる長い髪の……おそらくは女性。
ふと見ると、足元は魚のそれ。
——?!
私の顎に手を添え、彼女はくちづけた。
柔らかな唇が私の唇を開き、空気を送り込む。はじめは恐々と、次第に力強く、私は彼女と繋がってゆっくりと呼吸する。
——ああ、これが、人魚……
私の肩をぽんぽんと叩き、くちづけを終えるとニコリと微笑み、しなやかに身体を波打たせて、深い方へ消える。
私は彼女を見送ったあと、逆の方へと水を掻いた。
*
海面に顔を出して、今何時? と大声で訊くと、もうすぐ2時!と灯台が答えた。
4時に駅前が通れなくなるというから、そろそろ陸へ帰らなければならない。
接岸しているテトラポットから埠頭によじ登ることにする。
腕に力が入らない。やっとのことで埠頭に立つと、今度は足が重く、動かない。
そうこうしているうちに、雅也がワイバーンに乗って灯台から降りてきた。
「はい、着替え」
「ありがとう」
ワイバーンのハーネスにくくりつけた鞄を外して、タオルを出す。
無計画に泳いでしまったから、小さなタオルしかないけれど仕方ない。
ついでに鞄からスマートフォンを取り出して、着信がないことを確認。また戻す。
「……寒くないの?」
「ちょっと寒い、かな?」
「火を起こそう、焚き木拾ってくる。……着替えとけよ」
*
雅也の起こした火に、ワイバーンのかれは少したじろいだ。でも、それもすぐに慣れた。
火を囲むと、着替えた洋服が暖かい。
「あ、そうだ」
鞄から出した長いビーフジャーキーを、ワイバーンの口元へかざしてみる。
「食べる?」
かれはフンフンと鼻を鳴らしてから、そっとそれを咥えると、丸呑みした。
見ていた雅也が、
「なにそれ」
と覗き込む。
「おやつに食べようと思って持ってきたの。食べる?」
鞄から出して、手渡す。自分の分も出して、焚き火にかざす。
「炙った方が美味しいよね、きっと」
「そうだな」
上の方を持つか、下の方を持つか、で、私たちは議論した。そして、好きな方でいいんじゃね?という結論が出て、大笑いした。
「はーバカだよねえ……!」
「……どう、少しはスッキリした?」
「……」
「……穏やかじゃないだろ、メールで『消えたい』なんて寄越されたらさ。あちッ」
油が弾けた音がして、雅也はジャーキーを持つ手を持ち替える。
「……ごめんね」
「いいけどさ」
「もう大丈夫だから」
「ああ、うん」
——現に生きよ
また、あの声が聞こえた。
「ねえ雅也」
「ん?」
「……現実ってどこにあるのかな」
ーーーーーーーーーー
#6
僕は息を止めて未生を見た。
眠れずに僕へメールを送ってきたり、話してみるとやたらとはしゃいでいたり、逆に疲れ果てていたり。
それらが、彼女が自分に幻種の血が濃く流れていることを知ってからの出来事だということに、僕は気づいていた。
DFT鑑定を受けた、ということは、“鑑定を受ける必要があった”ということだ。
彼女のお父さんやお母さん、そのご先祖に何があったか彼女は言わないが、まあ……想像には難くない。
しかし、その質問は想定外だった。
「……幻種ってさ、”幻”って書くよね?」
慎重に考え考え、僕は手に持ったジャーキーを軽く振りながら続ける。
「ゲートが開くまで、僕ら人種は、幻種の存在を《まぼろし》だと思ってたんだって。見たって証言した人もいた、絵画にも物語にも描かれた、けれどそれは全部妄言で、ファンタジーで、フィクションだとされてたんだ…… 」
焚き火が、ふっと静かになる。
「おそらく、君のお祖母さんが、君を幻界に近づかないようにさせてたのも、その名残りだよ。お祖母さんが若い頃、いきなり“妖精”がホンモノだと発表されたんだ。価値観の転換についていけなかった人は、否定的になっただろうね……」
最初に焼べた薪は炭火になり、ちりちりと鈴のような音を立て始めた。
僕の横で、ワイバーンが静かに翼を開き伸びをして、また翼を閉じる。僕がジャーキーをかじると、かれは首を伸ばしてきてフンフンと鼻を鳴らした。残りのジャーキーをその口に放り込んでやると、ゴクンと丸呑みする。
「おかしいと思わないか?このワイバーンの存在だって、昔は《まぼろし》だったんだ。じゃあ、今ここにいるかれは《まぼろし》かい?違うだろ?」
未生は頷いて答えた。
「違うね」
何かがふっきれたような微笑みが、炭火に暗く照らされている。僕はなんだか少し居心地悪くなって、目を逸らした。
「僕らが触れられるものは現実だ、でも、触れられない現実だってちゃんとあるんだよ。見えなくても、聞こえなくても、存在している現実がある。……僕にわかっているのは、そこまでだ」
*
3時半には駅前を抜けた。
ビル街は静かに眠っている。
そこを飛んでいるのは僕らだけだった。
未生は僕の後ろで、ずっと黙ったまましがみついている。
ベルトのような彼女の細い腕と、ぴたっと背中にくっついている身体の柔らかな束縛を、僕は一生忘れないだろう。
それは確かな現実だ。
東の空に現れた濃紺から白磁へのグラデーションが、ふしだらで清らかなセンチメンタリズムを呼ぶ。
*
アパートの駐車場が空いていた。そこに着地する。
「はいお疲れさま。……未生?」
「……う、ごめん、寝てた」
「ゆっくりおやすみ。鍵、持ってる?」
「えと、うん、鍵ある。……ねえ、雅也ぁ」
「ん?」
未生は、黙った。
そして微笑むと軽く首を振った。
「……なんでもない、今日はありがとう。おやすみぃ」
「なんだよ。じゃあ、またな」
「うん、またね」
ふぁーあ、とあくびをしてアパートの階段へ向かう彼女を見ながら、僕はワイバーンを飛び立たせた。
ハンドリングカフェの苦いコーヒーを飲んで帰ろう、と思いながら、僕は背すじを伸ばして北への風に乗った。
(了)