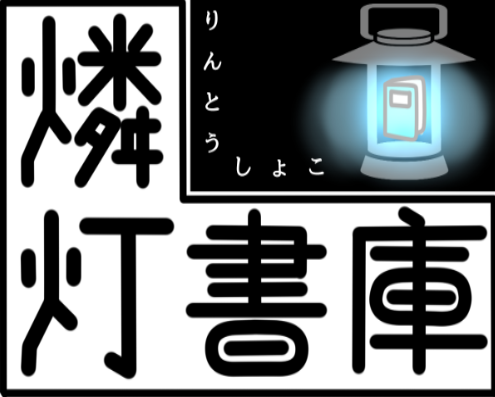夜明けの軋み 3話 秋、鬼灯投稿日:2018-03-04 |  |
「浴衣って、意外と暑いでしょう?本当はもう少し涼しくなってからの方が着やすいんですけど」
夕方といえど、まだ外は明るく、蒸し暑い。
この和室も、風が抜けるとはいっても吹き抜けるのは熱風、部屋が涼しくなるようなものではない。
小夜子が、言い訳のようにそう説明すると、浴衣を羽織った理人は前を合わせながら微笑んで答える。
「私は大丈夫。あまり汗をかきませんから」
「そう……よかったわ、父の浴衣を取っておいて」
「一度着てみたかった。コレわかります、オビですね、腰に締めます」
「待ってください、それは合わせが逆……左前、と言って、左側を胸につけるように合わせるのは、死者のための着方なの。貴方は右前……そう、そうです」
彼女もニッコリと微笑んだ。
帯の半分を理人の肩へかけ、両脇の腰骨をそっと触って帯を巻く位置を確認する。
背中側へも腕を伸ばして、帯を巻いていく。
「……少し締めますね、苦しかったら、そう仰ってください」
*
時山は新しいだけの街ではない。
寺社仏閣にも名高い戦国武将が祀られていたり、有名な書画が奉納されているところもある。
中でも300年の長い歴史をもつ文化財が、『八千代ぼんぼり』である。
初秋の鬼灯祭りは、鬼灯に見立てた小さな提灯を下げて燈籠町の仲通りを散策する、時山をあげての伝統的な祭りだ。
一時期出足が伸び悩んでいたが、幻族の観光客が増えたおかげで、祭りも賑わいを取り戻しつつある。
小夜子は、理人に対する警戒と親愛が入り混じった奇妙な気持ちを、とりあえずそのまま脇に置くことにした。
仕事柄、幻界からの移住者たちと毎日たくさん接していることで、偏見のようなものはないと言ってよい。
”警戒”とはただ、率直な本音が見えない彼に対するバリアのようなものだ。
それは時間や言葉を重ねることで変わってゆくのかもしれない、と多少の経験をふりかえって小夜子は思う。
*
浴衣の二人がバスを乗り継いで降りた停留所は、メイン通りからは少し離れていた。
大燈籠まで歩くことにして、二人は人の流れに沿った。
「ちょうちんいかがですか!」
幼稚園児だろうか、自分の頭とあまり変わらない大きさの提灯を掲げた女の子が寄ってきて、理人の袖を引く。
「ちょうちん!ちょうちん買ってぇ!!」
理人は、子猫に絡まれて困っている大型犬のような顔をして、小夜子に助けを求めた。
小夜子は腰をかがめて目線を合わせると、少女に話しかける。
「あなたのおうちで作っているの?」
「そう」
すると少女は急にモジモジとして、おかあさんがね、とか、ほおずき、とか、口の中でもごもごとつぶやき始めた。
小夜子はクスクスと笑って訊く。
「おいくらかしら?」
「1000円!」
小夜子が懐から財布を出そうとするのを制して、理人は袖下から小銭入れを出した。
「まいどあり!!」
少女が、おかあさーん!いっこ売れたー、と人の間を縫うようにして去るのを見送って、彼は手にした提灯を目の前に掲げてまじまじと眺めた。
「LEDを使ってる、安全です」
「……ちょうど日が落ちましたね、歩きましょう」
理人は頷く。
そして小夜子との間に提灯を持ち、二人の足元を照らした。
*
田生瀬川にはポツポツと屋形船の灯がともっている。
大燈籠にたどり着く頃には、人出もピークに達していた。
浴衣の人族に混じり、民族、ならぬ、幻族衣装でお洒落したマーメイドやエルフが連れ立って、大燈籠を背景に”八千代ぼんぼり”と書かれた看板の横でスマートフォンをかざし、写真を撮っている。
そこから田生瀬川沿いの遊歩道に連なる石燈籠の列と、さまざまな屋台。
焼きそばを分け合うノームたちの陽気な笑い声。
輪投げに興じるジャイアントは、そのリーチを活かして一等のゲームソフトを狙っているが、難しそうだ。
わたあめをねだる幼子。
金魚すくいの手伝いにウンディーネを呼び出したイフリートと、困り顔の店主。
理人が白い狐の面を買ってかぶってみせると、小夜子は笑いながらその面をそっと横にずらす。
小夜子は小鳥のかたちをした薄荷パイプを買って、首からぶら下げた。
混雑した往来で理人の半歩後ろを歩きながら、慣れない下駄で遅れがちな小夜子は、彼の帯にそっと手をかけて話しかける。
「ずいぶんとデミの方々もきていらっしゃるのね」
「ビザをとって此処へ来るような者たちは、人界の出来事に興味津々ですから……もともと幻界では毎日がお祭騒ぎのようなものです」
「貴方も毎日お祭り騒ぎを?」
「私は……少し離れて、眺めます」
静かに微笑んで続けた。
「くつろいでいる鹿の群れに、虎が近づいたらどうなりますか? たとえその虎が空腹でなかったとしても、鹿はくつろぐのをやめてしまうでしょう」
小夜子は目を逸らし、それにすぐ答えることはしなかった。
「たこ焼き、食べたことあります?」
*
人混みの中、水路の端にあるベンチになんとか空きを見つけた二人は、そこへ腰掛けて休むことができた。
「では、さっきのイカ焼きが小さなクラーケンで、これは『タコ』」
「そうなりますね。タコは、あのイカよりも大きいんですけど」
「大きいと言ってもクラーケンほどはないでしょう?」
「ないでしょうね……」
顔を見合わせて笑う。
「幻界で、クラーケンを食べようと考える者はいないと思いますよ」
「そうです。日本人はなんでも食べてしまう、と、よく笑われるんです」
小夜子はたこ焼きを楊枝で刺すと、口に頬張った。
「れも、ふぉのおおらかふぁと……」
右手の掌を理人に見せ、ちょっと待って、の合図をしながら、彼女はたこ焼きをもぐもぐと咀嚼して飲み込んだ。
「そのおおらかさとチャレンジ精神が、幻界のみなさんを迎えるための良い力になったんだと思います」
その小夜子の様子に笑いを抑えながら、理人は渡されたたこ焼きにゆっくりと楊枝を刺して、口に入れる。
「……美味しい」
小夜子は横から理人の顔を覗き込んだ。
「嘘。ヴァンパイアにとって、人間の食べものは無味乾燥なんでしょう? 研修で学びました」
「そうとも限りません。楽しく笑いあって食べるものは何でも『美味しい』と言って嘘ではありませんよ」
ふたりの前を通り過ぎる観光客が連れたブラックハウンドが、理人に気づくと立ち止まり、唸り声をあげて牙を剥いた。
主人はその頭をゴツンと叩き、理人たちに何度も頭を下げて立ち去った。
「……貴女も知っているように、私たちヴァンパイアは、実体を持つデミ種や人間の生気を奪って生きています。しかし、デミ種には特殊能力をもつものが多く、しばしば抵抗されます。だから、私たちはこれまで何百年も人界に忍び込んで、人間の生気を奪って生きていたのです」
観光客の往来が減ってきた。
ベンチもちらほらと空きが増えている。
「私たちに、人間を魅了する力があることは知っています。私たちはそれを利用して、難なく獲物を手に入れることができます、彼らはひどく酔っているときの様子で寄ってきて、私たちのなすがままでしたから。……嫌ですね、こんな話は。やめましょう」
「いいえ、知りたいわ。聞かせてください」
理人はちらと彼女を見て、彼女の表情が穏やかであるのを見てとると、小さな声で、はい、と言い、目線を落とした。
「たいていの人間は、生気を吸われたあと、記憶もままならない様子でフラフラと帰っていきます。しかしまれに、帰る途中で力尽きるものもいた。例えばそれを、家族が仲間が気づきます。我々は断罪されます」
「……それで、各地を転々となさっていたのね」
「ええ。我々は、人間と共存できるはずもなかったのです」
彼は不意に顔をあげて、小夜子を見た。
「貴女は以前言いました、貴女の食べる命は話さない、と。覚えていますか?」
「ええ」
「我々の獲物は、我々にも理解できる言葉で話します。陽気に、思慮深く、感情豊かに話します。我々は彼らを知りたいと思います、でも、彼らが我々の獲物である以上、彼らは自然な姿を見せてはくれないのです……」
彼の唇が歪む。右手が動いて、歪んだ顔を狐の面で覆った。
「こうして、遠慮なく出歩きたかった。誰の邪魔もせずただ一緒にお祭り騒ぎがしたかった。そのためになら、毎日の食事などどんなにつまらなくても構わないのです」
狐面の下を伝った雫が、地面に落ちる。
「……泣いてらっしゃるの?」
「……」
「……そう」
「……」
小夜子は少しなにか考えていたが、突然立ち上がると彼の腕を掴んで曳く。
「あ」
狐面の彼の足元に、空になった紙皿と提灯が落ちる。が、彼女は無視してさらに曳き、歩き出した。
理人は慌てて提灯だけを掴み、小夜子の後についてゆく。
遊歩道を抜け、大通りを横切り、だんだんとスピードをあげ、最後は駆けるように、下駄の音を鳴らした。
橋をいくつも渡った。
はあはあと息があがる。
小夜子は呼吸と動悸の限界を感じて近くの暗い路地へ飛び込んだ。人気のないビルの壁にもたれ、乱れた浴衣の裾を直す。
彼もまた呼吸を整えながら、どうしたんですか突然、と言おうとしたが、口をついて出たのは彼女の名前だった。
「小夜子さん……」
「ね、内緒ですよ?」
いつかの彼がしたように、彼女は唇に人差し指を当てた。
少し緊張した面持ちで、それでも無理に微笑んでみせる。
そして、浴衣の襟をぐっと開き、彼の名前を呼んで続けた。
「お腹いっぱいには、ならないかもしれないけど」
白い首筋を露わにすると、生気が漂う。それは生き生きと脈打ち、食い荒らされたことのない澄んだ色をしている。
彼は小夜子の意図を理解して慌てた。
「ちょ、ちょっと待ってください、私は監察人とーー橘さんと、誓約しました。人の生気を吸わない、と。それが守れないなら、罰を受けることになる、と」
「大丈夫です、死なない程度になら、誰にも気づかれません。もちろん、橘さんにも」
彼女は理人を見上げて続ける。
「虎は鹿を追い詰めて殺めます。でも、貴方は虎ではありません……ヴァンパイアは人を魅了し呼び寄せて、その生気を奪うんでしょう? わたしはきっと、貴方に呼ばれたんです。貴方はなにも間違っていない、この世界が、もう少し貴方にとって住みやすくなるまで、わたしを……」
空腹だった。
満たされたかった。
ーー何年ぶりの獲物だろう
目の前で身を差し出している、獲物。
彼は、小夜子に対するその形容をおぞましく思い、身震いした。
あわてて眼を閉じたが、彼女の生気を遮断することはおろか、それはますます彼の本能に訴えかけた。
小夜子は手を伸ばし、彼の狐面を外した。
「やっぱり、泣いてたのね」
微笑みながら、手の甲で彼の頬を拭う。
彼の頭を搔きよせ、耳元で囁く。
「内緒です」
提灯が地面に落ちて、カタンと音を立てる。
二人の影が、一つに重なった。