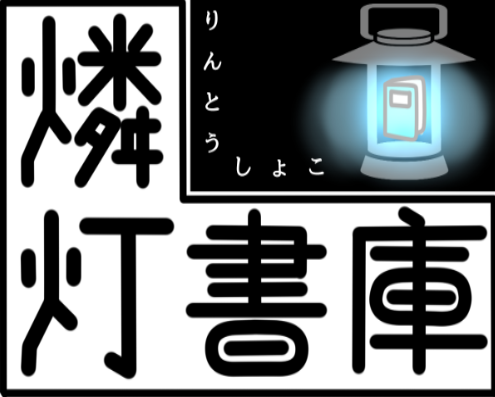無題投稿日:2017-05-01 |
あっ、と思った時には、すでに遅かった。
俺の古ぼけた革靴の下で、蜂は潰れていた。
長い手足をかすかに動かしてはいるが、臓物をさらけ出してはさすがに生きていられまい。
なんてこった。
日当たりの良い喫茶店の、窓際のこの席に着いた時から気にしてたのに。
*
暖房を求めてどこからか忍び込んできたこの死に損ないの、力なく窓辺を歩き回る姿。
時々眩しそうに外の光を仰いでは触覚を前足で磨き、また歩き出す。
行ったり来たりを繰り返す。
おい、来年の春までここで粘れよ。俺が差し入れに来てやるから。
「すみません、アイスコーヒーひとつ」
俺は床に落としたものを拾うふりして、シロップを奴の鼻先へひとしずく垂らす。
ーーおっ、なんだこりゃ、甘いじゃねえか。
ほらな、だから、もう少し、粘れよ。
春になればな、こんな胡散臭いモンじゃなくって、うまい花の蜜が吸えるんだぜ。
ーーそうだな、頑張ってみるか。
なのに。いや、だから、というべきか。
奴は飛び立ちやがった。
しかし、高度は上がらなかった。
フラフラと、俺の足にまとわりつくように飛び回り、俺は避けようと足を動かしたが、テーブルに視界を遮られた。
姿が見えなくなった。
あっ、と思った時には、すでに遅かった。
俺の古ぼけた革靴の下で、蜂は潰れていた。
*
俺はただ、それが動かなくなるのをじっと見ていた。
手足は宙を掻くようにかすかに震え、やがて動かなくなる。
ふうっ、と息を吹きかけると、居眠りから覚めたように、またかすかに動く。
何度かそんなことを繰り返して、俺はそれがとうとう動かなくなったのを確認した。
もう、そこにいる理由はなかった。
俺は伝票を手にとって、レジへ向かう。
たまたまレジに何人か並んでいた。
それは、葬列だった。
窓際の席に残してきたアイスコーヒーの氷が、冬の陽に溶けて、からん、と音を立てた。
それは鎮魂の鐘だった。
だとしたら俺は何だ。
俺はやっと自分の番が来たレジで焼香すると、その店を後にした。
(終)(初出 1998.12)