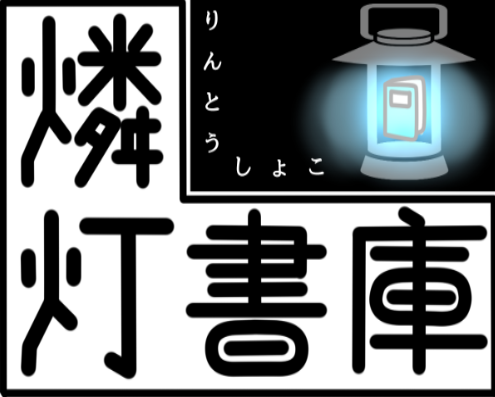大抵のことは愛でカタがつく。【4】BL投稿日:2017-12-04 |  |
「ポーズ集のモデル?」
「そう。あ、裸ね」
僕はメガネをずり上げた。
「いいんですか、僕、がりがりですけど」
サブカル系出版社に勤めるタカヤさんは、手を振って、ビアグラスをあおった。
「いいのいいの!セッちゃんがカワイイ系だからコタロウくんがシャープで丁度いい。その代わり、メガネは外してね……ん?外さなくてもいいかな?今、流行りだし?」
「え、セツも一緒なんですか」
彼女は大げさに驚いて体を反らした。
「えええっ!セッちゃんが言ってなかった?」
「いえ、『モデルのバイトやる?』って訊かれたから、『うん』て答えて、それだけ」
また大げさに頬を手で挟む。
「うわわ、どんだけ信頼関係育んでるのよ君たちは」
「信頼関係?」
「ちょっと、セッちゃん呼んでよ」
僕は、ロッカールームのドアを開けた。
「セツ?」
ソファにうつ伏せている。
気づいているのか、いないのか。
「セツ」
「睡眠中」
気づいていた。
「モデルバイトの話」
「あーしょうがねえな、行く……」
だるそうに立ち上がって、顔を擦る。
「モデル、君もやるの?」
「そ。絡むの」
「え。誰と誰が」
「オレとお前が」
「んん?」
よくわからないまま、彼について店に戻る。
「BLのポージングモデルだって、言ってなかったの?」
「先にそれ言ったら、嫌だって言ってたよ、きっと」
僕が断りそうなことだと知っていて、彼は説明を省いたのだ。
ーーなるほど、信頼関係ねえ。
僕の眉間にシワが寄る。
「ちょっと待ってください、『びーえる』って、なに?」
タカヤさんは頭を掻いて、
「あー、そこから説明しなきゃいけないか!なんにも知らされてなかったんだね、君は」
彼女は鞄からコミックを取り出して、僕に見せた。
「こーゆーお話が、BL」
僕はぱらぱらとめくって眺める。
「ああ、ホモセクシュアルのお話ですか」
人差し指を僕に向けて、彼女は強く言う。
「ホモじゃないの!B・L!『ボーイズ・ラヴ』よ!!」
「だって、そんな『ラヴ』なんて仄かなもんじゃないでしょ、本番ですよ、ほら。どこが違うんですか」
タカヤさんは頬杖をついて、僕を見る。
「美少年同士の恋よ。友情の延長にある愛なのよ、それがボーイズ・ラヴ」
「はあ」
僕は本を開いて、セツに見せた。
「つまり、僕と君とで、こーゆーのや、」
ページをめくる。
「こーゆーのをやってみせるわけ?」
「そ。」
「美少年?僕が?そんな華はないですよ」
タカヤさんがグラスを空ける。
「そこは、デザイナーさんが何とかするわよ」
「はあ……てことは、写真がそのまま載るわけじゃないんですね?」
「そう。こういう漫画を描く人のために、いろんなポーズをデッサンしてまとめた本があるのよ。そのモデルをお願いしたいの。写真に撮って、デザイナーさんがそれ見ながらデッサンするから」
セツが彼女に、次なに飲む?と訊いた。
彼女がグラスを指さすとセツはうなずいた。
さっきと同じビールの栓を抜き、注ぎながら僕に言う。
「拘束時間は結構あるけど、破格のギャラだよ」
「今、需要がおおきいからねぇ、景気がいいのよ……。ね、おねがーい、試しに写真撮って持ち帰ることになってんの!お願いッ!!」
「んー」
僕は少し思案して、答えを出した。
「じゃあ、一日だけならいいですよ」
「やった!!」
ガッツポーズ。
セツが僕の肩に手を回す。
「いいのかなあ?『ノーマル死守』なんでしょ」
僕は、笑う彼の腰に手を回して、身体をこっちに向けさせる。
「仕事だもの。……それに、ほんとに挿入るわけじゃないし……セーフってことで」
「ん、む、待てって、嘘っ、いきなりマジモード?!タカヤさん!!カメラカメんんっ……!」
ぼけっと眺めていた彼女を僕もちらと横目で見ると、慌てて鞄からカメラを出した。
僕はシンク横の作業台にセツを座らせて、シャツのボタンを開けていく。
女性と袷が反対で、開けづらい。
初めて触った彼の胸は、程よく筋肉質で程よく肉感的で、なるほどこれが客を満足させる身体か、と思う。
「値踏みしないでよ……」
見下ろす彼は少し拗ねたように言って、僕の頬を柔らかな手のひらで包む。
カウンターから上半身を乗り出したタカヤさんの、カメラの音が聞こえた。
「……なんで僕の考えてることがわかるのかな」
「指先は、おしゃべりだから」
「じゃあ舌は?」
彼は喉をさらけ出し、僕の頭を引き寄せて目を閉じる。
舌が彼を迎えに行くと、パシャ、という音とともにフラッシュが光る。
出会い、絡めあう。
舌を覆う唾液を搾り取るように吸い上げて、今度はその唇を食む。
シャッターを切る音が続く。
んっ……とセツの唇の隙間から吐息が漏れ、僕は彼のベルトを外しにかかる。
「ちょ……!コタ……やりす…ぎ……」
カウンターの内側の、ステンレスの作業台は今ちょうど空いている。
上半身を押し倒し、腕を押さえ、舌をねじ込んで黙らせる。
僕は彼の耳元で、
「ここなら低いから、誰か来ても見えないよ」
と囁くと、黒いパンツのホックを外し、ファスナーに手をかける。
ふ、とセツが息をついて力を抜き、僕は顔を離して彼を見つめた。
彼は顔を背ける。
僕は彼の前髪を掻き上げて、その顎をつかみ、こっちを向かせる。
「ねえ、セツ……」
呼びかけるとやっと、ゆがんだ目が僕を視る。
唇はなにか言いたげに、しかし力を入れて閉じている。
「セツ」
「……なに」
「どこまでやればいいの、この小芝居」
途端に、セツの顔がかあっと赤くなり、僕は突き飛ばされる。
「もういい!もういいよね、タカヤさん!!」
彼は起き上がって、はだけたシャツの前を合わせる。
タカヤ女史はカメラの液晶画面を順繰りに眺め、満足げに微笑んだ。
「ご苦労様」
僕はセツの顔を覗き込んで訊く。
「なんか怒ってるの」
「べつに!!」
タカヤ女史が帰り、僕らは片づけを始めた。
セツが洗った食器を、僕が拭き上げる。
「怒ってるじゃない」
「怒ってな……いや、怒ってる!」
「僕に?」
「そうだよ!」
セツは涙目で僕を見た。
「オレがバイだってわかってて、あんな本気で仕掛けてくるのは、ずるい!!」
「じゃあ、僕がノーマルだってわかってて、内緒であんな仕事やらせようとするのはずるくないの」
彼は黙って、うつむいた。
僕は布巾を置いて彼の方を向く。
「君の真っ直ぐな仕事を、いつも尊敬してる」
彼はふいに、僕の手から、拭きあげたグラスをとりあげ、泡の付いたスポンジで、また洗いはじめた。
「君に出会えてなければ、今の僕は、確実に無い。……毎日顔を合わせて一緒に働いてる仲間は今まで何人もいたけど、こんなに他人の中に踏み込んだのは初めてで、正直、僕もすこし戸惑ってるんだ」
僕が磨き終えた皿を彼は次々に再びシンクに戻すと、泡をつけて、やけになってきゅっきゅっきゅきゅ、と洗い、それを流して、僕の前にかしゃん、かしゃん、と置いていく。
「……僕は男性に性衝動を覚えることは全くないけれど、もし君が今後の人生でひどく苦しむことがあって、そこから救えるのであれば……、僕はためらいなく全力で君を抱くよ」
僕は再び布巾を手にして、彼が洗い終わった食器を磨く。
「だから、あんな君らしくないやり方は、もうやめてくれ」
最後の一皿を流し終えて、セツは顔をあげる。
ひとつ、ため息をつく。
そして何事も無かったかのように、僕を見た。
「わかったよ。じゃあさ、」
みるみるうちにいつもの笑顔になって、ニッコリ笑う。
「一発やらせて」
「ノーマル死守」
僕は真顔で即答した。
(終)(初出 2013-5-3 「大抵のことは愛でカタがつく。【4】BL」)