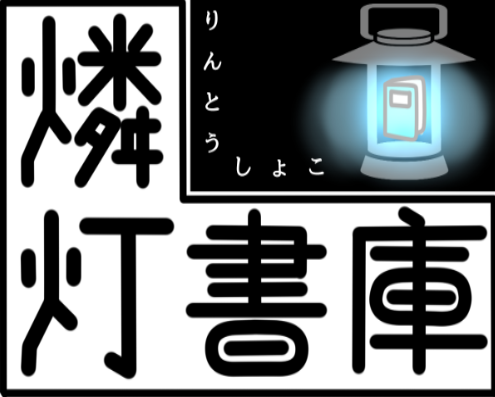夜明けの軋み 4話 冬、梅投稿日:2018-03-04 |
大晦日に降りだした大雪が、外出をためらわせていた。
高台に建つこの家からは、雪に覆われた紅が丘が一望できる。
サニータウンにはまだちらほらと空き地もあるはずなのだが、雪は全てを隠している。
年が明け、三が日の終わりが見えてきた頃になってやっと陽が差してきた。
しかし、あと三時間もすれば日没を迎えてしまうだろう。
小夜子の家の居間の掘りごたつは、正月だからといって特に何もすることのない二人を、こころよく受け入れていた。
「そろそろ買い出しに行かなきゃ……食料が底をついちゃうわ」
庭から採ってきた梅の枝を平べったい花器に生け終えると、小夜子は呟く。
理人が、読んでいた本から顔を上げて、窓の外に目を凝らす。
本を閉じると、パタン、と重い音がした。
「買い物をして荷物を運んだら、私は私の部屋へ帰りましょう。……父上の本棚のおかげで、たいへん有意義なお正月をいただきました。仕事始めには、館長と語りたい」
彼は、香我美の年越しカウントダウンイベントへ行こうと、この家まで小夜子を迎えに来たまま、近年稀に見る大雪に降り込められてしまったのだった。
小夜子の勧めもあって、空いている部屋に居候し、彼女の父が集めた時山の歴史や風土記、図録などをかたっぱしから読んでいくだけで、この正月は終わろうとしている。
*
理人は小夜子に何も語らないが、あの祭りの夜、恐る恐る口をつけた彼女の脈から吸い上げたわずかな生気で、彼の乾ききった身体がみるみるうちに潤い、満たされ、溺れそうにさえなったことを、忘れてはいない。
内緒、と彼女は言った。
それは彼女に、彼女が信頼する橘を裏切らせる行為である。
自らの欲望のためにだけ、彼女をそうさせることにはためらいがある。
彼は矜持をもつ貴族(ヴァンパイア)であった。
そんな彼を悩ましく誘うのは、最終バスへ乗った彼女の横顔だった。
停車するたび乗客が減っていくバスの一番後ろの席で、物憂げに、鳥の形をした薄荷パイプを唇に咥えながら、ぼんやりと窓の外を見つめる、その顔だった。
彼の視線に気づき、彼女はそっとパイプを離すと微笑んで言った。
『チーターに捕食されるガゼルには、モルヒネのような脳内麻薬が作用するんですって。ご存知?』
『……いいえ』
『そう』
小夜子は気怠く彼の肩に背中を預け、しばらく窓の外を眺めて黙っていた。
彼は、小夜子の表情を覗こうとしたが、その角度では無理だった。
ガタン、とバスが大きく揺れる。
『……ガゼルは……幸せを感じているんじゃないかしら』
『幸せ?まさか。喉を噛み切られようとしているのに、ですか?』
『ええ』
不意に、窓ガラスに映り込んだ彼女がガラス越しに自分を見ていることに気づいて、視線が合う。
『だって今、わたし、満たされているの』
*
玄関から外の道路まで雪かきをすることにした二人が外へ出ると、
「おっ、ハッピーニューイヤー!!なんだ、理人も来てたのか!」
橘が、通路の雪を踏み固めながらやって来た。
薄手のダウンジャケットに長靴、すっかり雪国仕様だ。
「……そりゃあひでえ正月だったなあ!」
彼らの年末年始を説明すると、橘は大笑いした。
二人もひとしきり笑ってから、
「理人さん、買い物、一人で行って来てくれませんか? 橘さんを置いていくわけには……」
「はい、構いませんよ。買い物ぐらい一人でできます」
と自信ありげに言ったものの、やはり不安なのか、買い物メモを小夜子に用意させてそれをしっかり握りしめ、彼は出かけた。
*
「お邪魔しちゃったかな」
掘りごたつに足を入れながら、橘はおどけたように言った。
「そんなんじゃありません……もっと早くても良かったのに。毎年元旦に来てくれるじゃないですか……」
小夜子は向かいに座り、いつものように灰皿を用意しながら応じる。
橘は脱いだダウンジャケットのポケットから煙草を出した。
「こんな雪深い僻地にホイホイ来れるかよ……しかし、まさかお前らがデキてたなんてなぁ!いや、実はあんまり驚いてはいないがな」
一本咥えて、軽く笑いながらライターの蓋を、キン、と弾いた。
オイルライターの匂い。
小夜子は、こたつの脇に常備したセットで日本茶を淹れる。
差し出される香ばしい緑茶の香りが、油の匂いを追いやった。
「……どうするんだ、現行法じゃ、ヴァンパイアの結婚は認められていないぞ」
小夜子は後れ毛を撫でながら、ちらと橘の顔を見る。
「そんなんじゃないってば。橘さんが考えてるようなことは、なにも」
「……お前はその顔で嘘をつくんだな」
「嘘なんかついてません」
「そうか、しかし、黙ってることはあるんだろう?」
小夜子は橘から視線を逸らさず、微笑みを湛えたまま、何度かゆっくりと瞬きをした。
橘もまた容赦なく、彼女を捉えて離さない。
「……わかってるのか、今はまだテスト期間だ。ここでトラブルが起きてみろ、理人とお前だけの問題じゃない、人界に来た幻族全体がそういう目で見られるんだぞ。
お前だってあの仕事してりゃわかるだろ? あっちにもこっちにも火種がある、だからこそ、今までの努力が水の泡にならないように、俺たちも幻族(あいつら)も踏ん張ってるんじゃねえか……!!」
点けたばかりの煙草をもみ消して、橘は身を乗り出した。
「あいつが時山に来た時から知ってるんだ、理人が悪い奴じゃないことは俺が一番よく知ってる。お前がバカじゃないことも。だからお前たちには幸せでいてほしいんだよ……!」
小夜子は唇に力を入れて目を逸らすと、縁側の向こうを眺めた。
沈みかけた夕陽が、雪の街を赤く染めている。
「牙を抜かれ、首輪をつけられた日々が、本当の”幸せ”であると?」
小夜子が俯く。
「……橘さんに、迷惑は、かけません」
「そういうことじゃない」
沈黙が続く。
橘はまた煙草を一本取り出した。
茶色のフィルターを下に向けて炬燵のテーブルの上に、ストン、ストン、ストンと叩きつけながら、言葉を探している。
先に口を開いたのは小夜子だった。
「わたしね、橘さん……もう時山は、昔の時山じゃないと思うの。今年の鬼灯祭りをご覧になった?道ゆく人の半分は幻界の人達だった……見たこともないような光景も……」
信号待ちをするバイコーン、その横には観光バスが並ぶ。
水路にせり出すような古民家オープンカフェでは、石燈籠の薄明かりの下で、ウンディーネたちが水遊びをしている。
白く光る魔法陣を描いて、じゃあねバイバーイ!と放課後の学生のような気楽さでその中に消えたのは、耳の長いエルフだった。
「わたしたちとあの人たちの間にあるのは、文化の違いです。だったら、お互いを大切にして一緒に生きることはできるはず」
*
橘は靴を履きながら小夜子に言った。
「まあ、すぐにどうにかできることでもない。まずは何より実績だ。時山のヴァンパイアはホラー映画のそれとは違うってことを証明するんだ。世論を納得させるには、それしかない。慎重に行動しろよ」
「はい」
「……迷ったら相談してくれ。悪いようにはしない」
彼女の瞳がみるみるうちに潤んで、弱気が溢れそうになった。見られたくないのだろう、深々と頭を下げる。
橘は、それを見ないふりをして玄関を出た。
——あとはこいつらの判断だ
高台から見渡す紅が丘はすっかり暗くなっていた。
雪の中に燈るいくつもの灯が、それぞれの家に生活する人々を想像させる。
橘は夜空に両手を伸ばして、ううーん、と伸びをした。