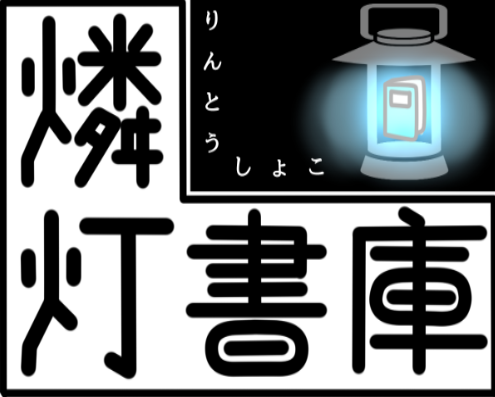夏の夜に寄せて投稿日:2017-05-01 |
だから明日は台風が来るっていう夜に給食室の壁によじのぼったりできるのよ。
「なんか言った?」
「ううん、何にも」
この人の好きなものはあたしの好きなもの、この人のしたいことはあたしのしたいこと。
あたしの真ん中のどーんっていうところにいるこの人について行くんだから。
彼が先に給食室の屋根から非常階段へ体を伸ばして乗り移る。
「来れる?」
「うん」
全然怖くない。
「懐かしいな」
「うん」
「よく怒られたよな」
「うん」
カンカンカンと音を二重に響かせて、三階、四階、鍵のかかった金網の扉を乗り越え、屋上へ。
強い風が髪をかき乱す。
昼間はゴミのように見えるあたしたちの生まれた街が、すくい上げたくなるような光の海になって、すぐ下に広がっている。
チカチカ瞬いている街灯、赤から緑や黄色に色を変えるネオン、あったかい家庭の団欒の灯。
あたしたちはどこへきてしまったんだろう。
「きれい」
「……」
彼は給水塔のはしごに手をかけている。
あたしは慌てて後に続いた。
さすがに囲いのない塔の上では、十分な広さがあると言っても足がすくんだ。
風に押されて闇に飲み込まれてしまう。
怖い。
膝が震える。
「おいで」
この声だ。
インチキ催眠術師のようなこの声に。
あたしの真ん中のどーんっていうところにいるこの人について行くんだから。
彼の脚の間に座る。
ここにいるとあたしはあたしじゃなくなる。
頭のてっぺんまであたしはこの人になって、何にも考えなくていいんだ。
この人の好きなものはあたしの好きなもの、この人のしたいことはあたしのしたいこと。
彼の手がシャツのボタンを外し、直の肌に触れるのを感じて、彼の唇を唇で塞ごうとしたそのとき。
「どうした?」
「ううん」
あたしは見てしまった、あの花火を。
じっと目を開けたまま、唇を重ねていた。
小指の爪ほどの、遠くで上がっている花火。
こんな強い風に流されもせず。
音さえ聞こえないほど遠くのあたしにも見えるように。
まっすぐに。
整って丸い、大きな、花を咲かせて。
ひとりで。
ーーああ、そうか、そうだよね。
あたしは震える膝に力を込めて立ち上がった。
怒号が聞こえるけれど、強い風にかき消される。
あたしは服を整えると、勇気を出して頭を巡らせた。
(終)(初出 1997-8)