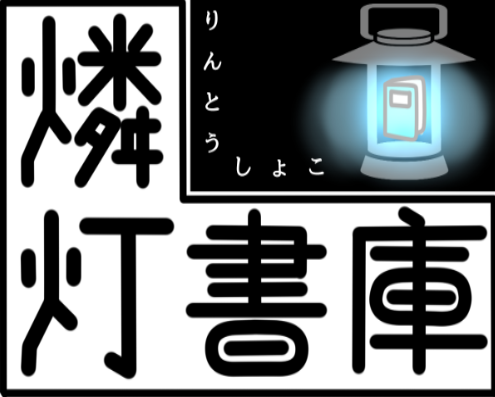踏み出すのは足、繋がるのは…【前編】投稿日:2017-05-01 |
駅前マンションのエントランスから出てきたマコは、通りの祭囃子にため息をついて、もうすぐ夫となる人の手を握りなおした。
彼はマコの不機嫌そうな顔に気づき、背を丸めて覗きこむ。
「どうしたのマコちゃん?」
自分の長いウェーブのかかった髪を耳にかけながら、ショートボブのマコの耳に向かって小さくない声で訊く。
「どうする、どっちに逃げようか」
「渡ろ、向こうへ渡ろう」
マコはデニムのショートパンツから伸びた足でつま先立ちになり、彼の耳へ向かってメガホンをつくる。
駅前通りは、今日だけ歩行者天国になっている。
【ぴかぴか祭り 今年も熱い!みんなで熱い】
あちこちに張られたポスターに、去年の夏祭りの写真と、星の姿をした男の子『ピカリくん』というキャラクタの絵が描かれている。
冴えない商店街、祭囃子に混ざらないサンバのリズム。その後ろからよさこいの鳴子が追ってくる。小学生の吹奏楽が、軍隊よりも規律なく、しかしそれぞれには緊張した様子で、有名なアニメーション映画の主題歌を鳴らす。
年寄りや子ども連れがほとんどの見物客たちは、歩道を占領してビデオカメラやスマートフォンを掲げている。
数人が、サンバとよさこいの間が開いているのを見計らって、道路の反対側へ渡ろうとしていた。マコと田端もまたそれに続き、タイミングを待つ。
「やっぱり、朝早くに出かけちゃえばよかった」
「しょうがない、朝っぱらから盛りがついてたんだもん」
「猫ね、猫の話」
「そうそう、もちろん猫の話」
面白そうに笑う彼の横顔を睨み、新居で『盛りがついた』自分の姿を思い出す。田端の顔が近づき、囁く。
「うちの猫はさ、鏡に映った自分の姿見て、興奮するんだよねー」
くっくっ、と笑う。
前にいた人々が道路を渡り始めたのに気づき、マコは彼の手を引く。
「早く、行くよ」
渡りきると、先を行った人々が右へ向かったのと反対に、左へ足を向ける。
高校生のカップルがべたべたとくっつきながら歩いてきて、すれ違いざま、女の子がマコを見た。顔を見て、それから繋いでいる手を見て、その先にある彼女の連れを値踏みした。
少しの嫉妬を含んだ視線。
『どした』
『なんでもなーい』
半笑いで言うような声が後ろから聞こえてきて、マコは奥歯を噛む。
「……いい歳をした女が、若づくりした男と手なんか繋いでみっともないわよね」
若づくり、と聞いた彼が眉毛を下げてシュンとしたのを視界の隅に見る。
しかし、手を離したら、せっかく手に入れた温もりが消えてしまいそうで、彼女は汗ばんだ手を握り直す。
「歩く?」
いつも無精な彼がそう言ったことに少し驚く。
「任せる」
応じて、マコは前を向いた。
* * *
3年前の夏。
マコは、イベント会社の資材搬入作業の日雇い派遣として働いていた。
あの夜は、8時で終わるはずのコンサートが延長したため、荷揚げが終わったのは10時だった。
たまたま他の現場で知り合った大学生と同じグループになったので、飲んで帰ろうという話になった。
うんざりしながら居酒屋へ入って、トイレで汗だくの作業着からジーンズとTシャツに着替える。
座敷でぐだぐだと飲んだあとは、軽く酔いも回ってすぐ解散。
ひとり最終の地下鉄で自分のアパートへ向かう。
昼間から痛かった足へ、つま先に鉄芯が入った重い仕事用のブーツが追い打ちをかけて、片足を引きずるように歩いていた。
マコの部屋に一番近い地下鉄の出口には、エレベーターが無い。改札を出たマコは、仕方なく手すりを伝って階段をあがる。作業着を入れたトートバッグが邪魔だ。
右足の、土踏まずと反対側の骨が悲鳴をあげていた。少し地面につけるだけで顔がゆがむほどに痛い。
踊り場で出口を見上げ、外が土砂降りの雨になっていることに気づく。
降りてくる人は、濡れた傘を畳んで持ち、足下も雨に当たって色が変わっている。
彼女は折りたたみ傘すら持ち歩いていなかった自分を、ひっぱたいてやりたい気分だった。
ーー強い雨……だったらエレベーターの出口から、タクシーに乗ればよかった……
今いる場所から階段を下って長い廊下を歩き、エレベーターへ向かっても10分近くはかかるだろう。
それに、これではきっとタクシーを待つ列も長くて、いつになったら帰れるかわからない。
そこまでする気力は、もうなかった。
『ごめん、夜遅くほんっとに悪いんだけど、こういう事情なの、迎えにきてくれないかなぁ…』
マコはいくつか、電話の台詞をシュミレーションしてみた。しかし一番親しい女友達にも、いざ電話をかけようとすると、できなかった。
ーー頼まれたらイヤとは言えないのに、頼れない
こんなとき、気兼ねなく頼れる家族か恋人がいたら。
もう10年近く、実家には帰っていない。
2年半付き合った恋人とは別れて4年経つ。
親密な間柄の人間にどんな声をかけていたか、すっかり忘れてしまっている。マコは情けなくて泣きたくなった。
やっと頂上にたどり着くが、絶望的な雨風を見て、立ち尽くす。
ーー待っていたら、小降りになるかな……ああでも、南の方に台風が来ているんだった
庇の下で待つ帰宅客らは、雨が強く吹き込んでくると階段をおりて踊り場に戻った。
スマートフォンをのぞき込んだり、時計を見たりして、どうやら迎えを待っているらしい。
頂上に残されたマコは、軽く身体が濡れて、決心した。
ーーだめだ、一刻も早く帰ろう。10分だ、10分で部屋に着く
足の痛みに、10分で着かないことは予想できたが、そうとでも思わないと踏み出せなかった。マコはかがんで、ジーンズの裾をブーツの中に押し込んだ。
心持ち息を止めて一歩踏み出す。予想以上の雨の強さで、体中が痛かった。アスファルトから跳ね返る泥水が、ブーツを汚す。
三歩歩いて、すでに髪の毛は濡れて頬に張り付いた。
五歩で、Tシャツがぴったりと張り付いて、体の形を浮かび上がらせる。濃い紺色の厚手のTシャツだから下着が透けはしないし、一瞬人目を気にしたものの、すぐに意識を足元へ向けなければ転んでしまいそうだった。
マコはふいに、先週の飲み会での会話を思い出す。
『マコさんはほんっとに強いなぁ!』
リーダー格のベテランが、ビール一杯で顔を真っ赤にしながら訊く。
『出先に無理な注文つけられたときも、俺なんかより対応厳しかったもんな!』
『えー?でもマコさんてぇ、コトバはキツイけどすっごく優しいんですよぉ』
若い事務員が、隣の主任にお酌しながら言う。
『言葉がキツくっちゃ内容なんかアタマ入ってこねえだろ? そこいくとお前は小悪魔系だよなあ、言葉遣いはてれんてろんしてる癖に無理難題言ってくるからねえ、もう……』
『やだぁ、ひどい主任ー!!』
背中をばしんと叩き、主任が苦笑する。
『うちの奥さんなんか、言葉キツイ上に無理難題だから!どうしたもんかねぇ』
『たいしたことでも無いのに文句言うんだよねえ』
『そうそう!いっつもイライラしててさ』
ーーそんな愚痴を言いながら、迎えにきて!って言われたらすぐに駆けつけるんでしょ……
その場で見せた愛想笑いの代わりに、ここで毒を吐く。
20メートル歩き、スーパーの前を素通りする。
自動ドアから出てきた客が、びっくりして彼女を見た。
ずぶ濡れの彼女はむっとして、罪もない客を睨み、撥ねた雨水で泥だらけの足を交互に前へ出す。
ーーああイヤ!!もう独りは嫌だ……!!
泣きそうになりながら必死に唇を噛んで足だけを動かす。
暗い街灯の住宅街に差し掛かると、身体を打つ雨が止まったのに気づいて、マコは顔をあげた。会社帰りらしき男が、黙って黒い傘を差しかけている。
それが田端との出会いであった。
マコはとりあえず無視した。
ーーまずい、変な男。部屋までついてこられたらどうしよう……
彼女が歩くと、男も歩く。彼の身体は左半身が濡れ始めた。
「あの……結構です。一人で帰れますから」
低い声でマコは言い、頑さを隠さずに男を見上げた。
頭ひとつ分、彼女より身長が高い。髪は肩上ぐらいの長さはあろうか、後ろで一つに縛っている。痩せ型の、どことなく全体的に地味な男である。
柄のない茶色のネクタイは、飾り気のない彼の襟元にふさわしく収まり、その上から地味だが安くはなさそうな黒いジャケットを羽織っている。
傘のない方の手に、ブリーフケースと、製図用紙を入れる筒を持っている。
このあたりで見覚えがない、しかしまじめそうな顔だ、とマコは思った。
「でも、傘、ないんでしょ」
田端は傘を差しかけたまま、彼女を見下ろして言った。彼女は、それまでの苛立ちをぶつけるように睨んで返した。
「私の家まで来るつもりですか……?」
「そうか、それで怒ってるのか、わかった。じゃあ、傘持って行きなよ。この傘、骨一本折れてるんだ。返してくれなくていいから、使ったら捨てちゃってね!」
合点した、という顔で、彼はうなずく。
彼女が、え?と思う間に、彼は傘をマコに押し付けると、荷物を抱えて一歩踏みだそうとした。
「待って!」
マコは田端の腕を掴んだ。
振り向いた彼が、驚きながらマコの顔に焦点を当てる。
彼の目を見て、そして逸らして、その腕を掴む自分の手を見た。
「ごめんなさい……やっぱり一緒に来てもらっていいですか」
溜め息まじりに、マコは言った。
のぞき込むように田端が、
「怒らない?」
「怒らない」
「一人暮らしなんでしょ、用心するのは良いことだ」
静かにそう言って、傘の柄を彼女から受け取り、腕を差し出した。
「掴まれ、松葉杖だと思えばいい」
彼は彼女に配慮して、わざとつっけんどんに言う。
マコは彼の好意に甘えた。
「すみません……」
二人は黙って歩いた。
この嵐は台風のせいだとか、どのあたりに勤めているかとか、そういった世間話をするには悪い印象を与えすぎてしまったと、お互いに思っている。
田端が歩幅を合わせて歩いてくれるおかげで、彼女はそれ以上濡れずに済んだ。
足の痛みは相変わらずだが、躍起になって歩かなくて済むのが、なによりありがたい。
マコは自分の、男性を見る目の無さに舌打ちしたい気分だった。
ーー悪い人じゃなかった……こんなだから、誰とつきあっても長続きしないんだ
全面的に負けを認めている。それは田端にとっても同じことで、彼は彼なりに、彼女に手出しをしたことを悔やんでいた。
ーーいつも余計なことして、結果、不評を買うんだよなあ……
彼としては、もし彼女が男性だったとしても傘を差しだした。
この嵐の中、足の悪い人間がずぶぬれで歩いているのを見過ごすことは、彼にはできない。彼はそういう性質であった。
しかし、同じ親切でも、女にとって別の意味を持つケースがあることを、ここ数年でやっと彼は理解した。
二人はそれぞれ、苦い思いを飲み込んだまま、嵐の中を歩く。
駅の出口から一度だけ左に曲がって、彼女のアパートの前に着く。そこまで二人は、一言も口を開かなかった。
「じゃあ、……お疲れさま」
田端は、どんな挨拶でこの場を締めるべきか迷って、そう口にした。
マコは、感謝の言葉が過去形で口をついて出そうになって、慌てて別の言葉を探した。
できるだけ柔らかな、できるだけ自然な、誘いのセリフを血眼になって探した。
「あの……あなたの服、濡らしてしまったから、タオル使ってください」
「いいよ、もう帰るだけだし」
「いえ、寄ってください」
片足を引きずりながら、単身者用の古いアパートの、いくつも並んだドアを通りすぎて、一番奥のドアに鍵を差し、彼女は田端を手招きした。
マコにしてみたら、生まれて初めての、相当な自棄だった。
田端を玄関に入れて、ドアを閉める。
「ちょっと待っててくださいね」
水で脱ぎにくいブーツを無理やり脱ぐと、足裏に痛みが走る。
玄関先の壁にもたれ、マコは冷たい雨をたっぷりと含んだTシャツを脱いだ。
それを床に落とすと、重い音がした。
ぼたん、とも、べちゃん、とも聞こえた。
タンクトップを居酒屋で脱いだことをすっかり忘れていたので、通販の安いブラジャーだけになったが、今さらどうでもよかった。
立ったまま右足を庇いつつジーンズを脱ぐのは難しかった。
床に座り、脚から皮を剥ぐように脱いだ。
不純だろうと何だろうと、需要と供給が一致すれば契約は生まれるはずだ、とマコはつたなく計算する。
田端は黙ってそれを見ていた。
彼もまた、男としてよこしまないくつかの計算を始めたが、下着姿になったマコを上から下までひととおり眺め、自分のジャケットの水滴を払った。
奥へ入ったマコが、タオルを手にして戻ってきた。
「これで……」
「ありがとう」
伸ばした手に渡されるかと思いきや、彼女がそのタオルで田端の頭を拭き始めたので、彼は手を引っ込めて、彼女の顔を至近でまじまじと見た。
「誘ってるの?」
直球で田端は訊いた。
「そのようですね……独りで眠りたくない気分なんでしょう」
マコは他人事のように淡々と答え、彼の左半身にタオルを当てていく。
「あとで訴えたりしない?」
「訴える……乱暴されたとか嘘ついて?」
「そうだ、君が悲鳴のひとつもあげれば、俺はなんにも申し開きできないんだし」
マコは、ジャケットの袖口から彼の顔に、ゆっくりと視線を移した。
田端が靴のままたたきに、マコがあがりかまちにいるせいで、身長差はマコの方がほんの少し上だ。
彼の首に手を回して、顔を引き寄せる。
「……ごめんなさい、こういうとき、何て言ったらいいかわからないの」
唇を合わせ、舌の先で彼の唇をそっと舐めた。
柔らかく、つるりとした感覚は久しぶりで、これが食べ物だとしたら美味しいかもしれないと思う。
舌をちろちろと動かしてみると、彼の唇が僅かに開いた。
彼はマコに委ねた。気のないそぶりで応じ、彼女の出方を窺った。
ーーこれはなんだ。痴女か?
下世話な週刊誌にでも出ていそうな体験談であるが、そういったことに縁のない彼は都市伝説だとしか思っていなかった。
それにマコは見た目も仕草も、暇つぶしに男を部屋へ連れ込むような奔放な女性には見えない。
据え膳食わぬは……というには、少々腰を据えて懸からねばならぬ案件だと思われる。
鼓動は勝手に高まるものの、これによって抱えるリスクを考えると、欲情だけで押し倒すわけにはいかなかった。
「おうちに誰か待っているとか?」
控えめな田端の反応に、彼女が疑問を投げた。
「ううん。先月、離婚したばかりでね」
「だったら……あがってください。なんだか、情けなくって、一人でいるの怖いんです」
「情けなくて怖い……?」
彼女は頷いて、身体を離した。
「そう。そうとしか言えない……よくわからない、だから。……もちろん、無理にとは言えないけど」
田端は、彼女が軽い女に見えないのは、不器用だが丁寧に言葉を探そうとしているからだと思った。
マコは下着姿のまま、右足を軽く引きずって奥の部屋へ入って行った。
(【後編】へ続く) (初出 2014-8-3)