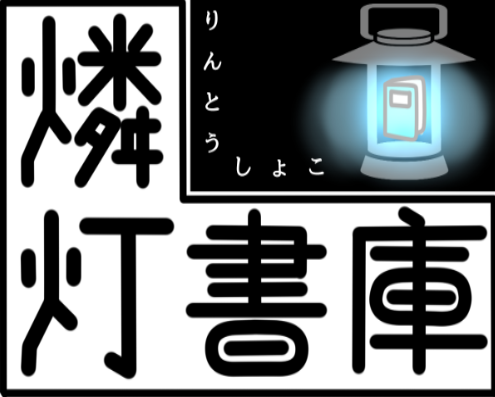贄の仔育(こそだて)投稿日:2017-05-01 |  |
或る山深い峡谷に、春の一ヶ月だけ、陽のあたる谷があった。一ヶ月、芽吹き花咲くうちにも桜が最も優美なので、『櫻乃郷』と呼ばれていた。
深く険しい山の中、そこに踏み入る人間は道に迷った猟師だけ。
麓の村では、古くからの言い伝えにより、聖域とされ、畏怖されていたからだ。
今年の櫻の季節、そこには一頭の竜が巣作りをしていた。
腹が膨れていて、気が立っていた。
身の丈は大の男で三人分ほど。広げた翼をばっさと振るうと、その風すらも凶器になる。
言い伝えを守らずに踏み込んだ人間は、彼女の餌食になった。
やがて彼女は草木を集め、石で丸く囲んだその中心に卵を産んだ。
身体が軽くなったので、動物や人間を取ってきては、自分が食べる分までを干物にして、とっておいた。
竜はその行動が何を意味するか知らない。
ただ、そうするべきだと知っていた。
*
竜が獲物を探していると、村外れの山道に人間を見つけた。
女だった。子供をふたり、連れていた。
周りを見渡すに他の人間は見当たらず、竜に気づいた彼らは走って逃げた。
女は子供たちを岩陰に隠し、背中の弓を取って引いた。
しかしうまく当たらない。
竜は女に体当たりし、足の鉤爪で引っ掴んだ。
女は抵抗した。しかし、到底逃げられる力ではなかった。
竜は羽ばたいて舞い上がり、泣き騒ぐ子供らから離れ、飛び去った。
巣に下りた竜は、動かなくなった獲物をすぐ脇の小さな洞穴にそっと置く。これは干物にしない。
今朝、殻の中でカリカリと引っ掻くような音がしていた。
殻から出てくるものには、まず柔らかく瑞瑞しいものを食べさせなくてはいけないからだ。
卵に近寄り、前肢でつついてみる。コツコツと返事があった。
まだ時間がかかりそうだ。
もう少し新鮮な肉を獲りに行こう、そう考えて竜は二度三度と翼をはためかせて、飛び立った。
夕暮れが迫っている。
*
女は意識を取り戻した。
横になっている自分の胸元に、何かが寄り添ってきたからだ。
冷えて、ゴワゴワしていて、濡れていた。
目を開けてみると、それは猫ほどの大きさの仔竜だった。
息を呑んで動けずにいると、それが震えていることに気づく。
自分が居るのは暗い洞穴で、外は雨が降っていることにも気づく。
——そうだ、竜に捕まって……
はっとして胸元の仔竜から飛びのく。身体中の痛みに呻き、その場に崩れ、横になる。
女のその呻き声に、仔竜は目を開いた。
そして、甘えた声で鳴いた。
仔竜がまた女の元へ寄って暖をとろうとするのを、女は怒り、かっとして、仔竜の尻尾を掴み、洞穴の壁へ投げつけようとした。
仔竜はきいきいと鳴いた。
——親竜に見つかってはいけない
幸いにして気配はない。
荒げた息を鎮め、深呼吸し、女はそれを抱きしめて再び横になった。
——いつか、家に帰るんだ
女はそれだけを思って目を閉じる。
*
一日経っても、二日経っても、親竜は帰ってこなかった。
その間、孵ったばかりの仔竜は普通なら死んでしまうところを、女の胸で暖をとり、生き永らえることができた。
女は仔竜とともに雨水を飲んで飢えをしのぎ、なんとか歩けるようになった。
5日後、やっと陽が射し、洞穴の奥に何かの干物を見つけた。
匂いを嗅いでみると、なんとか食べられそうだった。
——毒味をさせよう
女はそれを齧りきり、膝に乗せた仔竜に与えてみる。
仔竜にはまだ歯が生えていなかったために、うまく食べられず吐き出した。
もう一度女は干物を齧り、噛んで柔らかくして食べさせる。
——私の子供たちにもこうして食べさせた……
思い出すまいとしても、思い出す。
うつむくと涙がこぼれ、仔竜の頭を濡らした。
仔竜は雫の落ちてきた方向を見上げたが、その口へ無理に入れられた干物肉をはむはむと噛んでは飲み込んだ。
*
親竜が帰らずに二週間が過ぎた。
女は、かの竜はもう帰らないだろうと思う。
女を襲ったその日の宵の口、再び村はずれを訪れた竜は、そこで肉になっていた。
母を連れ去られた子供達が泣きながら村へ戻り、村では腕の立つ者たちを集め、即座に討伐隊を結成していたからだ。
元から竜や大型獣の狩で生計を立てている狩猟民族である。討伐隊は、その気性の荒さに辟易しながらもなんとか倒した。
「この種の竜は夜目が効かぬのに、なぜ」
「大方仔竜でも生まれたのであろう、春だというのに痩せこけておる」
そして女は、自分ももう帰れないのかもしれないと思う。
干物の中に、人間の肉でできたものがあることは、半分ほど食べてから気づいた。
しかし女はそのあとも、仔竜とともにそれを食べていた。
食料が底をつきそうになって、女は狩りを思い出す。
*
女は武器を作ったことはなかった。
見よう見まねで、木の枝と石とつるで作った急ごしらえの弓矢と槍。
日々、他にすることもなく、女はそれらを磨き上げていく。
狸や狐、うさぎや雉なら獲れるようになった。
仔竜はじゃれつきながら、女の狩の足元についてきては邪魔をした。
女は「やめろ」と言いかけて、口を閉じる。
人間の言葉では話しかけまい、と決めていたからだ。
彼女は足で軽く蹴り、仔竜を退かせた。
やがて夏が過ぎ、秋になった。
女の武器は鋭さを増し、狩りは精度を増した。
仔竜は女とともに狩をするようになり、狼や熊までを獲物とするようになった。
実際、仔竜は仔と呼べないほど成長していたので、食料も多く必要とするようになったのだ。
宵の口に、甲高い声で遠吠えをすることも出てきた。
本能が仲間を求めているのだろう、と女は思う。
だが、竜の仲間に未だ出会えない仔竜は、女と同じほどの体長になったにも関わらず、その胸に寄り添って眠った。
時折、女は思う。
自分はもう、人間と暮らせないのではないか、と。
特に会話もせず、目配せや身振りだけで共に獲物を追い込めるような意思の疎通ができる竜との生活が、当たり前になってしまった。
しかし、この竜にとって、それでいいのだろうか、と。
*
冬が来た。
竜の動きは鈍くなり、洞穴の奥を少し掘り下げて、そこにうずくまった。
この地の竜は冬眠する。
女はしばらくの間獲物を運んでやったが、とうとう目覚めなくなったので、そっと枯葉や毛皮を被せてやった。
雪が降り積もる。
洞穴の入り口は雪にほぼ蓋をされ、腰を屈める出入り口だけ確保したが、外にでても雪は深かった。
秋に獲り溜めて作っておいた干物を、毎日一口ずつ食べながら、女は武器を作り続けた。
それに疲れると、洞穴の壁に絵を描いた。今度はそれに飽きて、熊の骨を削り、笛を作った。竜の遠吠えに近い音が鳴るようになるまでには、いくつも作って、いくつも壊さなければならなかった。
——この仔が目覚めたら、飛び方を教えよう、否、教えることなど何もない、お前は飛べる、と見守ってやれば良い。
*
風向きが変わる。
雪解け。
谷の草木が一斉に芽吹いた。
生き物は目覚め、穴ぐらから這い出て、春の光の眩しさに目を細めた。
仔竜ももぞもぞと動き出し、女の姿を見て一声鳴いた。
女が弓矢を持って外へ出ると、仔竜はのそのそとついてくる。
柔らかな草の上を、女は駆けた。
腕を広げ、陽光の温かさを一身に受けた。
仔竜も駆けながら、翼をパタパタと振っている。
女はそれを見て谷を出ると、丘を駆け上り、駆け下りた。
振り返ると、後を追ってきた仔竜の足が浮いた。
——それだ!そのまま……!!
女は右腕を振りかぶるように、竜のいる方向から前方へ回した。
竜は一度、二度と大きく羽ばたき、その勢いを強めながら女へ向かって突進してくる。
一、二、三、女が草に伏せたその上を、唸りをあげて飛んでいく竜。
——飛べ……!
だんだんと高度を増し、ぐるりと大きく回りながら、女の頭上を飛んでいる。
女は奥歯を噛み締める。
急いで懐から笛を取り出して、思い切り吹いた。
見晴らしの良い丘から、周辺の山々に、竜の甲高い遠吠えがこだまする。
しばらく待ってみるが、応答はない。
もう一度。
と、かすかに、遠吠えが聞こえた。
もう一度、今度は長く吹く。
長い応答が聞こえた。
——仲間がいる
女は、地に降りた竜に駆け寄って抱きしめた。
「君の仲間が来る、一緒に空を駆けろ」
鼻筋を撫でながら、わかるはずもなかろう、と思いつつ、言って聞かせた。
仲間の声は近くなる。
女は草むらに身を隠して、青空に浮かんだ小さな黒い点が、だんだんと近づいて来るのを見た。
竜が吼え、仲間も吼え声を返した。どうやら、姿形は似ているようで、女はほっと一息つく。
竜は女の方を見た。
「行け」
女は微笑んで、振り上げた腕を仲間の方向へ下ろして見せた。
ためらうように何度か振り返ったが、竜は仲間に合流して、舞い上がっていく。
太陽に向かって消えていくようで、その眩しさに女は目を細めて見送った。
*
女は静かな谷へ戻った。
「ああ、桜が……」
思い出すのは、小さな仔竜を抱いて、初めて洞穴から出た時のことだった。
白い花びらが舞っていた。
谷の中心を覆う大きな枝振りの桜の樹に、そこだけ陽光が照らしていた。
その時と何も変わらない、全く同じ光景がそこにあった。
ただ、腕の中にあった弱く小さな命は、もうない。
女は奥歯を噛みしめて堪えた。
なにを堪えているのかわからなかった。
ただ、こぼしてはいけない気がした。
それはあの仔への裏切りだと思った。
そう思えば思うほど、堪えることは難しくなった。
御免なさい、と呟きながら、一粒、こぼれた涙を拭う。
——村へ帰ろう。
女は長くなるかもしれない旅の支度を始めた。
(終)(初出 2017-4)