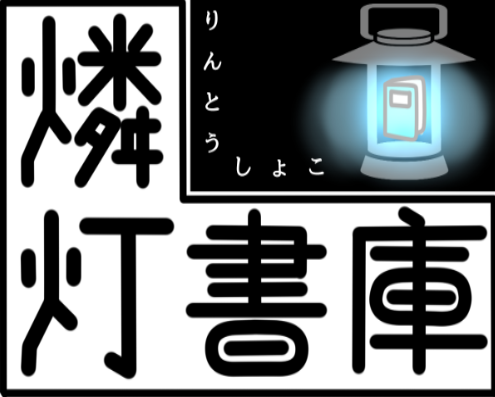夜明けの軋み 5話 春ふたたび、玉蘭投稿日:2018-03-04 |  |
ふと、理人が顔を上げて呟いた。
「桜はまだ咲きませんね」
彼は日当たりの良い廊下で、本を読んでいた。
淹れた緑茶を彼に差し出しながら、小夜子は長いスカートの中で足を崩す。
「今は玉蘭かしら」
「ギョクラン……」
「白木蓮とも呼ばれます。良い匂いなの」
桜と対になるように、大きな木が白い花を咲かせている。
理人は縁側へ出るとサンダルを履いて、玉蘭の下まで歩いた。
「桜の花は我々を見下ろすが、玉蘭は空を見上げている。今にも飛び立ちそうな形で咲いています。良い匂いです」
小夜子もそれに続いたものの、冷たい風に腕をさする。
「……まだ上着がないと寒いのね」
理人は羽織っていたカーディガンを脱いで、黙って小夜子に手渡した。
『暑さも寒さもあまり感じないのです、我々は……』
以前、理人が言っていたことを思い出す。
それが本当なのか、やせ我慢しているのか、小夜子にはわからない。
しかし、ヴァンパイアのバイタルーー体温や血圧、心拍などーーが、自分たちに比べてとても低いところで安定していて、人間用の測定器では誤差が出るのだということは学んで知っていた。
「ありがとう」
小さく言って微笑み、大きなサイズのそれを羽織って腕を通す。
そこに彼の体温は感じられなかったが、小夜子は呟いた。
「温かい……」
*
吹き込む冷たい風に、小夜子は目を覚ました。
「起きて!雷です!!」
理人の声で座卓から頭を上げ、慌ててあたりを見回す。
居間でうたた寝をしてしまっていたのだと思い出し、庭へ目を向ける。
暗い空からポツポツと窓を叩く雨の粒。激しい風に揺れる庭の草木。
春の午後のあまりの変わりぶりに混乱する。
ーーそうだ、洗濯物
小夜子が立ち上がると同時に、理人が腕いっぱいに洗濯物を抱えて、姿を見せた。
切れ切れだった雨音はザーッと連続し、降りしきる夕立を知らせた。
「これ、持ってください、雨戸閉めます」
小夜子に洗濯物の山を預けると彼は、居間の明かりをつけたあと、廊下に面した6枚の雨戸を引いて閉める。
洗濯物を座卓の上へ下ろして、小夜子はまだぼうっとしたまま、ぺたりと座り込んだ。
理人も、ふう、と息をついて小夜子の向かいに座り、自分の洗濯物をその山の中から引っ張り出しては、畳みはじめる。
「ああ、気づかなかった、眠ってしまったのも、雷も」
小夜子もタオルだけを選んで畳んだ。軽くあくびが出る。
と、重い和太鼓のような響きに続いて、空を引き裂くような雷鳴。
びくっと微かに震えた小夜子と、微動だにしない理人。
顔を見合わせた途端、明かりが消えた。
「「あ」」
同時に声が出て、小夜子は暗闇に腰を浮かす。
「懐中電灯か、スマートフォンで明かりを……どこだったかしら……」
「待って、少し待って」
理人が彼女を声で制し、何やらブツブツと唱え始めた。
日本語ではない。
英語やフランス語、小夜子の知るヨーロッパの言語ではない。
もしかしたら、ラテン語が近いのかもしれない。
声はだんだんと近づいてきて、彼女は理人の気配を隣に感じた。
やがて手をすり合わせるような音が何回かして、ほわん、と部屋の空気が動いた。
と思うと、握りこぶし程度の弱い光の玉が現れた。
青白く、脈打つように、柔らかな光がゆっくりと明滅する。
小夜子のびっくりした顔が青白く浮かび上がり、彼は微笑む。
「理人さん、魔法が使えたんですか……」
「私の名前をご存知ですか?」
「Licht ……ドイツ語で、光、だったかしら」
「そう。私が扱えるいくつかは、光の魔法です。幻界では”光に餌食わす者”と。……しかし、これは光が弱い。すぐに消えてしまうかも」
「綺麗……」
小夜子はそれに触れてみた。
指先に、ほんのり温もりが伝わってくる。
これが理人の体温だ、そう思って小夜子は泣きたくなった。
理人の体温になりたい。
混ざり合って溶け合って、ずっと彼の中にいたい。
小夜子は、温かなその輪郭を撫でながら言った。
声がかすれる。
「ねえ、満たしてください」
「私を?貴女を?」
「どちらも、よ」
温もりから離した手を、かろうじて灯っているその青い光が、理人の手へとつないだ。
「それが……貴女の望みなら」
理人は小夜子の華奢な手首に頬ずりしながら冷たい唇を寄せる。
彼にはわたしの生気が見えているのだろう、と、見えない小夜子は思う。
貧血にも似た一瞬の目眩に、んっ、と声が洩れる。
ちらりと彼の目が小夜子を捉えた。
小夜子のぼんやりした視界の隅に入ったそれは、いつもの色ではなかった。
金色の瞳が、冷たさと諦めをたたえて彼女を見ていた。
彼女は、これが捕食者の色、と思う。
座っていてさえ、だんだんと怠く、脱力しそうなほど生気を吸い取られていく身体。
反比例するように、熱い奔流のように流れ込み、指先までを満たしていくもの。
それは、死に近づけば近づくほど、甘美に、じんわりと胸の奥を焦がす。
ーーわたしは犠牲者なのかしら
思考の断片。
それはゆらゆらと、彼女のあずかり知らぬところへと流れ、消えていく。
ーーわたしは老いて死ぬ、彼は老いない、長い長い人生
これもまたゆらゆらと、どこかへ消えた。
ーーヴァンパイアにとって子は、彼の一番の理解者たりえる
このハウツー本の見出しのような断片だけが、小夜子の蕩けた頭にこびりつく。
崩れ落ちた彼女を支えるように理人が抱きとめた。
小夜子は、手首からその唇が離れるのを切なく思いながら、暗闇に墜ちていった。
*
「小夜子さん、小夜子さん!」
目を開けると、心配そうな理人の顔がぼんやりと見える。
「無事でしたか?!」
「う……ん、無事」
「この前より細い脈から吸ったのに……ああもうやめましょうこんなこと」
自分の膝に彼女の頭を乗せ、おろおろと顔を覗き込んで髪を撫でる彼の目は、晴れた空の水色だ。
時間が経つにつれ、小夜子の身体はぼうっと温かく、お湯の中に浮かんでいるような感覚になっていた。
心地よさに浸りながら、大丈夫だと笑って理人を安心させようとする。
その彼の顔の向こうに、浮かぶ光を見つけた。
紫色に煌々と光っている。
「あ、光……。さっきと、色が変わったわ」
「小夜子さん、貴女のマナは、私には赤く見えます」
「理人さんの青と、わたしの赤で、紫なのね……」
嬉しい、と呟きかけ、それを飲み込んで違う言葉を選ぶ。
「素敵だわ」
「そうですか。大して役に立たない魔法です。もっと誰かを癒したり、誰かを守ったりできる魔法もある。しかし私は生きるために奪うだけです、他の命を、奪うだけ」
「そんな……」
小夜子はふらりと寝返りを打って、理人の膝に頬を寄せた。
「わたしにもね、魔法が、使えるの」
「人族の貴女に?魔法が?知りませんでした」
「結果が出るまで、一年ほど時間がかかります。でもその魔法に、貴方はきっとびっくりするわ。貴方の協力が必要です」
「私の?」
「ええ……うまくいくかは……わからないけれど」
半身を起こして、小夜子は悪戯っ子の顔で理人を見た。
理人は真面目に彼女を見返す。
「そんな大魔法を……?」
小夜子はくすくすと笑った。
あまりに楽しそうに笑うので、彼もまたくすくすと笑った。
ひとしきり笑ってから、小夜子はコホン、と咳払いをすると、起き上がって恭しく告げた。
「いいですか、わたしにまかせてくださいね」
彼は神妙に頷いた。