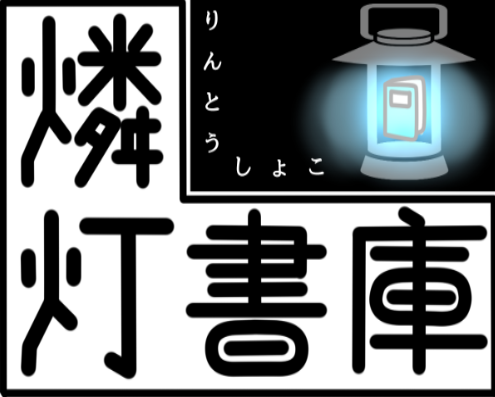大抵のことは愛でカタがつく。【2】匂い投稿日:2017-05-01 |  |
「例えば?」
僕はグラスを磨きながらセツに尋ねた。
彼はカウンターに座って、いつものように頬杖をつき、左手の爪を眺めながら答えた。
「玉」
「ほう、ほう、なるほど。理解した。じゃあね、……ま、ま、ま……卍固め」
「普通にプロレスの技じゃん」
「でも、ほら、裸で卍固めを想像してごらんよ! そしてこの語感で最後の一押し」
「いいだろう、コタロウは初心者だからよしセーフ。卍固め、目隠し」
「やだ、目隠し、やらしい。しかも早い。さすが」
「でしょう?」
彼はにこにこと笑っている。
「し、し、し、……し?」
「時間制限20秒」
「ええっ?し、し、……締まりがいい!」
「そのまんまだからダメ」
17、16、15、と、腕時計を見ながらのカウントダウンが始まる。
「そ、そんな!あ、じゃあ、締まる!!」
「セーフ!!」
ふたりで、ほう、と息をつく。
「……なにをやっているんだろうね、僕たちは」
「ええ?なにって……しりとりってこういうもんでしょ。仕方ないよ、客商売だもん、来ないことには始まらないじゃない」
彼は金髪を耳の横でくるくると弄ぶ。
僕は灯りに透かして、グラスの色を確認した。
店のグラスは、マスターがこだわってあちこちを探したものだそうで、それぞれに、色がある。
僕も初めは気づかなかった。
しかし曇り一つなく磨きあげ、毎日同じ灯りに照らして見ていると、ワイングラスたちは空色、ウィスキーグラスたちはオレンジ色、ブランデーグラスたちは草色、ショットグラスたちは薄紅色……と、わずかに、ほんのわずかに色が付いていることに気づくのだ。
「良い夜だなあ」
僕は呟いて、ひとり、しりとりの続きを考える。
締まる、る……
からんからからからん、と少々慌てた様子でドアが開き、女が飛び込んでくる。
「セツ!匿って!!」
まだ肌寒い初春だというのに、ショートパンツにシャツだけの、風邪でも引きそうな格好。
彼女の名前はルカ。る、ルカ。おお。
彼は、いらっしゃい、と言いかけて、止まった。
「どうしたの、鬼ごっこ?」
「高梨に、見つかった。アミと絡んでるとこ」
「なにやってんだ、バカ」
ルカは息を弾ませて、僕らのロッカールームに駆け込んだ。
セツが慌てて立ち上がり、出入り口のドアを開けて素早く周りを見回すと、「OPEN」の札を「CLOSE」に裏返す。続いてロッカールームに入り、なにやら、がしゃん、ばたん、と音を立てて、出てきた。
切羽詰まった顔でまっすぐこっちに歩いてくる。
「な、な、なに?!」
「ごめん、ちょっと我慢して」
僕をシンクへ追いつめ、どすん、とぶつかるようにいきなり胸ぐらを掴んだ。
僕はてっきり、殴られる、と思い力を入れて構えたが、彼は僕のワイシャツのボタンを飛ばして胸元を開いた。
「ええ……?」
顔を埋められ、
「ひゃっ」
妙な声が出る。
彼の髪からはココナツの甘い匂いがして、僕は不覚にも若干の反応を催す。
しかし、これは僕のお得意様である杏子さんという人妻が好むココナツバターを思い出したことに依るのであって、それはいわばパブロフの実験で証明された条件反射的反応だということを、もしあとで彼に問いつめられることがあるならば、声を大にして言うつもりであった。
僕は彼の意図するところを解っているのだ。
彼が少々の本気度をもって首から胸のラインに唇を這わせているからといって、それが芝居でなくてなんであろうか。
よし。
その途端、ドアが開いて、大柄な男が姿を現した。
「……」
無言で僕らを見つめている、らしい。
僕はメガネがずれているせいで、あまりはっきりと目視できないのである。
「い、いラっしゃい……ませ」
声が裏返った。
セツは顔をあげて、ゆっくりと振り向く。
「まだ、店、開いてないんだけど。……こんなときはさ、『お楽しみのところ悪いが』とか言うんじゃないの? ねえ、高梨さん」
「……ルカが来ただろ」
「ルカなんか、いっつも捕まんねえよ、どこをほっつき歩いてるんだかさ……もういいでしょ、やっとこいつがその気に」
高梨はガツガツと歩み寄るとセツの髪を掴んで引きあげ、
「裏、見せてもらうぞ」
冷蔵庫に叩きつける。
頭を庇って肩を打ったらしく、セツは肩口を反対の手でさする。
「平気か?」
そっと訊くと、唇を噛んで頷いた。
ロッカールームでいくつか派手な音をさせて、高梨が戻って来た。
「邪魔したな」
「ねえ、ルカなんかにかまけてないで、オレと遊んでよ……」
セツは高梨に近づき、身体を寄せ、甘えた声を出す。
「オレ、一回あんたのケツの穴にぶちこんでやりたいんだよねえ、あんたの大っ嫌いな男同士って奴でさぁ」
とん、とん、と何度か彼のベルトの上を人差し指でつつき、ベルトからワイシャツをなぞって上へあがると、喉元、顎をたどって彼の唇で止める。
「なあ、しゃぶってくれよ……そうしたら」
もう片方の手で首を引き寄せて耳元に囁く。
「この、図体の割にカワイイおくちの中に出してやるよ、にがーくて、濃いーのを、たっぷりね」
高梨はその手を掴んで投げる。
「……変態が。兄妹そろってクズだな、反吐が出る。マスターの贔屓だからって調子に乗ってると商売できないような顔にしてやんぞ蛆虫め」
「ありがと。顔だけで商売してないから問題ないよ」
セツがにっこり笑う。
隠しきれない怒りを声色だけににじませて高梨は、
「妹に言っておけ。他人の女に手を出すなって……今度やったら、ぶっ殺す」
静かに言った。
店の床に唾を吐き、店と僕らをひとしきり睨め回すと、彼はドアを開けて出ていった。
セツは床の汚れを淡々とティッシュで拭き取り、ゴミ箱に捨て、ロッカールームのドアを開けた。
「……もういいぞ、ルカ」
* * *
僕は、セツに借りたシャツの首まわりが少し気になって、もう一つボタンを外した。
そして、ルカにミックスナッツを差し出す。
「君たち、兄妹だったの?」
「ううん」
「戸籍も違うし、血のつながりも、もちろんない」
セツは自分とルカのグラスに、ビールを注いだ。
「……昔、一緒に暮らしてたの。でもお互いの恋人に見つかっちゃって、とっさに出た嘘が……誰にも内緒にしてね」
「うん。ああ、なるほどね。目のあたりがちょっと似てるもんね、そうだと言われたら、信じるかも」
セツは彼女のグラスに勝手に乾杯して、飲み始める。
「最後の頃は、ほとんどエッチもなかったな」
「そう、お互い、ヘテロに飽きてたからね」
「ヘテロってなに?」
「男女の組み合わせのことよ。ホモ・セクシュアルが同性間ペアなのに対して、異性間ペアをヘテロ・セクシュアルっていうの」
「あのころが一番仲良かったよね」
「そうそう、いつも一緒にDVD観てた……レンタルの店で、あいうえお順に借りてたんだよな」
「つまんない話だと、すぐに寝ちゃうんだよね、私」
「それでオレだけ、つまんねーなあと思いながら最後まで観ててさ、ちょうど観終わるころに、こいつ起きるの。『どうだった?』って」
顔を見合わせて屈託なく笑う。
そんなふたりを、”ベスト・オブ・偽兄妹”にノミネートしようと僕は思う。
年末の、なんとか大賞みたいに、新高輪プリンスホテルの飛天の間かどこかで、丸いテーブルを囲んで、血のつながらない兄妹たちが座るんだ。
もちろん、妹は皆、着慣れない華やかなイブニングドレスに身を包み、緊張した面もちの兄にエスコートされて、おずおずと着席する。
「アペタイザーには何がいいかな」
セツが顔を上げる。
「え? 何の話?」
「なんでもない」
僕はメガネをずりあげて微笑む。
グラスのビールを飲み干して、セツはルカの方に椅子を向ける。
「お前さ、アミには手ぇ出すなよ……まずいよ」
「あの子はあいつのものじゃないんだ、だいたい誰のもんでもないでしょ、もちろん、私のものでもね……それを、あいつにわからせてやりたい」
「けど、高梨はまずいって……あいつはこの街で生まれ育った奴なんだ。人脈も広いし、やってること正気じゃねえよ……お前だけじゃなくて、アミだってどうなるかわかんないぞ。それじゃ、意味がないだろ?」
僕はビールの瓶の栓をあけて、ルカと、セツのグラスに注ぎ足し、少し余った分を、自分の分のグラスに入れた。
ルカは煙草を取り出した。
僕はライターを点けてそっと差しだす。
「そうだコタロウ、あんたの禁煙、まだ続いてんの?」
「うん、今のところね」
「へえ」
顔を傾けて彼女が火を灯すのを確認し、僕はライターと入れ替わりに灰皿を差し出す。
「……シャブ漬けにされても、生きてる方が良いと思う?」
セツは目を伏せた。
「ねえ、セツ、わかるでしょ、私がどうして焦ってるか……」
ルカは、ごくごくと喉を鳴らしてグラスを空にする。
指に挟んだ煙草の、赤く燻る先端をじっと見つめる。
咥え、深く吸い込み、煙を天井の換気扇に向かって吐き出した。
照明のあたるところだけに、手先からたち上る蒼い煙が揺らめいている。
やがて灰皿に、まだ長い煙草を押し付ける。火が消えても、まだ安心できないというように、ぐりぐりとねじ込むように押し付ける。
「リミットは近いのよ」
静かに、椅子から降りた。
お尻のポケットから財布を取り出す。
「じゃあ、行くね。……コタロウ、ごちそうさま。あんた、サービスうまくなったね。……はい、ひとつはあんたのお小遣い。もうひとつはビール代。おつりは要らないよ」
一万円札を2枚、僕の前に突き出す。
金額の意味を測りかねてセツを見ると、受け取っておけ、というように頷く。
僕は深々と礼をする。
「ありがとうございます」
セツがルカの腕を掴む。
「待って、こっちおいで……いいか、絶対に無茶すんなよ? ……最近の映画って結構面白いんだ、知らないだろ……」
ルカは目を閉じて、セツの頬にすりよった。
彼の首筋に鼻先を埋める。
「ああ、久しぶり、セツの匂い、懐かしい。……おすすめの映画、探しといてよ」
「うん、探しとく」
ふたりは軽く、唇が触れ合うだけのキスをした。
そして、世界中を探してもそこにしか温もりがないというように抱き合った。
目を閉じて、お互いの匂いの中で安心したように、穏やかな顔をしている。
それはまるで、親を失った幼い兄妹が、ふたりきりで寄り添い眠っているように見えた。
僕は背中を向けて、客のために戸棚に買い置きしてある煙草をひとつ開け、火を点ける。
煙をゆっくり肺に入れ、吐きだしながら、このふたりにセックスが要らなくなった理由がわかった気がした。
穏やかな愛情に、性的衝動は起こりにくいと言われる。
劣情は、愛に劣るのだ。
「愛……」
僕は目を伏せて呟いた。
* * *
僕らはルカの姿を見かけなかった。
一週間、一ヶ月、三ヶ月、半年。
『身元不明の女性の遺体』という言葉を耳にするたび、僕はあの日のことを思い出す。
「もともと、おんなじ街に住んでても滅多に顔を合わせることがなかったんだからさ……まったく、またどこをほっつき歩いてるんだかね」
セツはいつもと同じように頬杖をついて、軽く笑った。
そしてカウンターに立てられた小さなカレンダーを手にとって、眺める。
「……もう週末かぁ、早いな」
彼は毎週末、DVDを借りに行く。
そして日曜日の夕方、ほとんど観ないままのそれを、返しに行くのだと聞いた。
愛の行方を想うとなんともやりきれなくなって、僕は戸棚にしまってある、とっくに湿気てしまったあの日の煙草に手を伸ばしかけ、やめる。
彼女にもらった僕の一万円は、その日のうちに使い切った。
「ねえセツ、しりとり、しようか」
僕が言うと、彼は余裕の微笑みを浮かべて、こっちを見た。
(終)
(初出 2013-3-27 「大抵のことは愛でカタがつく。【2】匂い」)