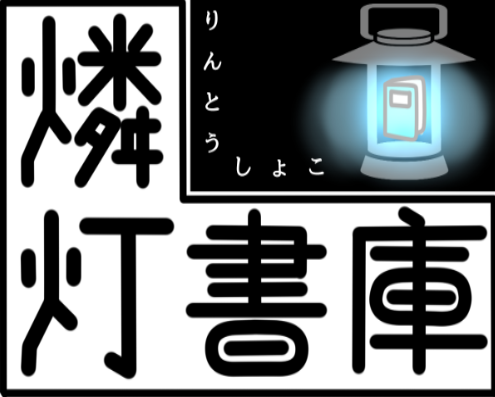夜明けの軋み 1話 春、桜投稿日:2018-03-04 |  |
【幻界ゲート】の発見と幻族の流入は、世界を騒然とさせた。
国や地域によっては排斥運動や虐殺まで行われたという。
しかし、日本では時の政府が、少子化問題の切り札として、いち早く幻界融和の政策を打ち出していた。
人口の流出を止められずにいた中規模都市であるこの時山市も、追って賛成を表明していた。
そのため、市に設けられた特区“香我美”を中心に、それまでの人々が物語や映画でしか知らなかったような風変わりな者たち、妖精、精霊、幻想生物、そして彼らが扱う綺麗な光や魔法陣などが街にあふれるようになったのだ。
ーー“夜明けの軋み”
幻界ゲートが開いた当時の流行語大賞だ。
日本人特有の好奇心はおおむね良い方向に働いているようで、この国は、明治維新以降久しぶりに訪れた夜明けに軋みながらも、社会の歯車を止めずにいる。
1.春、桜
「あ……」
散りはじめた桜の花びらが春の風に煽られて、縁側から、小夜子たちのいる和室へと舞い込んできた。
小夜子は、亡くなった父に誂えてもらった喪服の胸元を押さえながら、正座を崩して手を伸ばし、花びらをつまみ上げる。
橘は、黒いネクタイを外した。
そして、思い出したようにポケットからスマートフォンを取り出し、マナーモードを解除する。
それからは、座布団にしっかりとあぐらをかいて、差し出されたコーヒーをすすりながら、たった今線香をつけた仏壇を見つめている。
供物の果物とお菓子。
豪華な仏花。
位牌と線香立て。
そして、それでも空いてしまった空間を埋めるために置いた、デジタルフォトフレーム。
小夜子の父親の、笑顔が、真剣な顔が、遠くを見る顔が、5秒ごとに切り替わっていく。
二人はしばらく黙って、その顔を眺めていた。
「もう三回忌か。あっという間だな」
橘は礼服の胸元からオイルライターを取り出すと、その蓋を軽やかに親指で弾いた。
澄んだ音がして、かすかに油の匂いがたゆたう。
「うちの中も外も、いろいろとありましたから……」
小夜子の言葉にうなずきながら、橘は咥えた煙草に火をつけると、ゆっくりと煙を吐き出した。
小夜子は、橘が来た時いつもそうするように、座卓の上に出しておいた灰皿をそっと彼の方へ差しやる。
「ああ、本当にいろいろあった。ゲートが開いて、俺が『管理局』に異動して、おやっさんが倒れて……亡くなって」
「あっという間だわ、わたしだって誕生日に結婚して、次の誕生日には離婚して」
小夜子は、ふふふ、と笑った。
「お父さんも心配してるわね、きっと」
「ははは、箱入り娘が結婚したと思ったら、一年で出戻りだ!そりゃおやっさんも成仏できねえよ、はは」
「何も反論しませーん」
「いや、俺だってバツイチ4年目だ。ようこそバツイチの国へ!……と言っても、俺の方はクビになったんだから、お前とは違う」
「クビ?」
「そう。父親をクビになった」
「ああ、そういう意味」
小夜子は面白くない冗談を聞いたという風に、肩をすくめてみせた。
「……結婚なんて、ギャンブルよ。あの人につけられた痣や傷はまだ残ってるけど、良い勉強になったわ。あのときは本当にありがとうございました……いつかちゃんとお礼しなきゃね」
「お礼?何言ってんだ。おやっさんは俺にとっても親みたいなもんだったし、だったらお前は妹だろ……妹がDV受けてるなんてわかったら、放っとくわけにいかねえもん。気にすんな」
橘は大学卒業後、時山市役所の生活支援課に就職した。その時、手取り足取り業務を教えたのが小夜子の父だった。
業務だけではない。
公務員としての心得や、市民とは何か、時山の未来……居酒屋へ行くたび熱く語るのが常であり、家族ぐるみで部下の面倒をみる、古いタイプの男だった。
橘は小夜子に言ったことがある。
「おやっさんは面白いな、『日本を創った男たち』に出てきそうな昔の漢。俺の親父よりも父親みたいだ」
しばらくして橘は課を移動した。
しかし直属の部下でなくなってからも、彼はなにかと橘を可愛がり、家へ呼ぶことが度々あった。
橘もまた、愚痴や疑問を持ってきては、助言を求めたりもしていた。
それゆえ、二年前、小夜子のたったひとりの家族であるその父が脳溢血で亡くなったときにも、その後結婚した小夜子が夫の暴力から逃れようとしたときにも、橘はなにかと彼女の力になった。
大きな声で屈託無く笑う、頼りになる橘を、小夜子も兄のように慕っている。
「……なあ、お前、そろそろまた働かないか?俺んとこ、人手が全然足りないんだよ」
小夜子は、お団子にした髪の後れ毛を撫でながら橘を見た。
「幻界人界窓口管理局……ですか」
「うん。コーヒーのおかわり、貰ってもいいかな」
「はい、ちょっと待っててくださいね……」
小夜子は立ち上がって、台所へ消えた。
*
古い間取りのこの平屋は、小夜子の祖父が建てた日本家屋だ。
祖父や祖母、母までも、彼女が幼いころに亡くなっている。そして父も、もういなくなった。
持て余す部屋と広い庭を備えたこの家に、彼女は一人残されたのである。
この家は、紅が丘でも外れの方の高台にあって、周りにはまだ麦畑が広がっている。
しかし近年、このあたりの大地主がつぎつぎと世代交代をして、広い農地を売り払ってきたのだ。
紅が丘の中央を横切るように、高速道路もできた。
それにともない、紅が丘の一部を”サニータウン”と名付けて、大きなベッドタウンを作ろうという都市計画が進められている。
これまで売れた土地は、更地になった数年後に、新しい建材でできた建売住宅が次々と建てられた。
売れなかった土地は麦畑のまま、まだ多く残されている。
*
「市庁舎の隣のだだっ広い駐車場あっただろ、今あそこを地下に埋めて、その上に5階建のビルを作ってるんだ。で、ウチに来てた、あの……」
「デミ種の方たち、ですか?」
「そうそう、デミ種。あの人たちだけを集めて、ゆっくり手続きできる場所を作ろうって話。今度そこの一角に新設する『幻種総合支援部門』ってとこで俺は、政令指定種のヴァンパイアや喧嘩っ早い奴らのお目付役をするの」
「あら、初めて聞いたわ、その話」
「国の『幻界局』直轄でプライバシーの問題もあるから、あんまり他言はできねえんだ」
橘は、ずっと口許へ構えていた煙草を吸おうとした。が、灰が落ちそうになっていることに気づき、慌てて灰皿へそれを落とした。
そして目線を小夜子に戻すと、また口を開く。
「これから出て来るであろう問題に、さまざまな法整備を進めなきゃいけないこともあって、非常に忙しい。……それでね、事務処理だけでもお前が手伝ってくれないかなって思ってさ、こうやって声をかけているわけです」
「はあ……わたしなんかで役に立つのかしら、もっと仕事のできる方がいらっしゃるんじゃ……?」
橘は唇の端をあげてニヤリと笑うと、灰皿で煙草をもみ消した。
「まあなあ……けど、キャリアのある奴はいつ結婚して辞めちまうかわかんねえじゃねえか」
「ひっどい!……まあ確かに、わたしはもう結婚なんてうんざりですけど」
「な、頼むよ。お前なら対応も柔軟だし、頭だってキレる。俺はお前の能力を買ってるんだぜこれでも」
言い終えて次の煙草を取り出すと、彼はまた火をつける。
小夜子は、首筋に垂れた髪の毛をゆっくりと弄りながら、真面目な顔で床を見て黙っていた。
「危ないこととか怖いことはないよ」
「それはわかってるわ、橘さんはそんな仕事だったら私に振らないもの。……わかりました、いいですよ、やりましょう」
やっと橘は煙草を咥えた。
そして、ホッとした顔で煙を吸い込むと、ゆっくり吐き出した。