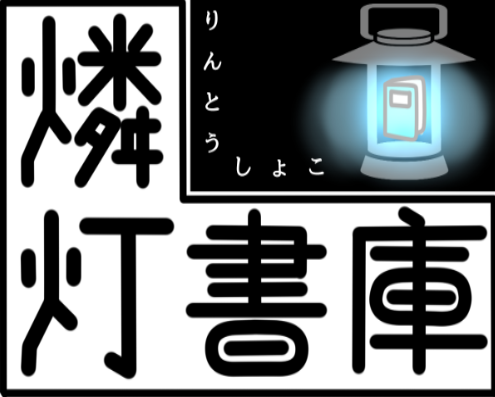夜明けの軋み 2話 夏、カンナ投稿日:2018-03-04 |
受付の混雑がひと段落して、小夜子はふう、と息をついた。
左手をひねって腕時計を見る。12時18分。昼休みの時間をとっくに過ぎている。
売店からパンでも買ってこようか、いつも空いてるうどん屋へ行こうか。けれど、銀行員のようなチェックのベストに半袖白シャツ、ベージュのタイトスカート——時山市職員の制服である——で、外に出るのは目立つ……。
カウンターの帳票を整理しながらぼんやり考えていると、そこへひとりのヴァンパイアが訪れた。
「こんにちは。監察人の橘さん、いますか?」
「ああ、理人さん、こんにちは」
小夜子が見上げるほどの身長は、2メートル近くある。
短い金髪に碧眼、色の白さは人の目を惹く。
彼が自分で決めた人界名は、理人・ポドルスキー。
年をとらないヴァンパイアだから、年齢は325歳だが、印象は人間でいうところの30代前半ぐらいに見える。
紺色の薄いTシャツにジャケットを羽織っているだけで、洋画の俳優のように華やかだ。
彼は最近頻繁に通ってきているので、小夜子にとっては馴染みの利用者である。
しかし、受付の奥にいるデータ整理のアルバイト女子達にとっては珍しいのだろう、口々に彼が来たことを小声で囃し立てては、照れ隠しに笑っている。
彼らヴァンパイアは、その特性から人々の恐怖心を煽らぬよう、監察人をつける条件での在住が許可されている。
その法律が施行されてから、これまで強制退去になったヴァンパイアはいない。
理人もまた、担当監察人の橘とともに煩雑な手続きを終え、時山に生活の基盤を作りつつあったのだ。
「お仕事、順調ですか……?」
「はい、毎日がだいたい順調ですよ」
「橘さん、いま外出中なんです」
「ああ、そうでしたか……待てば帰りますか?」
「あと1時間ぐらいはかかるかもしれませんね」
「1時間……」
そう呟いたまま、彼はじっと動かなくなってしまった。
確かに、一時間というと外へ出て暇つぶしするにも微妙な時間だ。
それに、もっと早く帰って来るかもしれない。
小夜子は背後の女子達を気にして少しためらったが、それとなく尋ねてみる。
「わたし、いまからお昼を食べに行こうと思うのですが、理人さんはもうお済みですか?」
「いえ、私は“お昼”を特に必要としません。でも、そうですね、少しお話ししませんか?」
「もちろん良いですよ、では……地下の食堂にしましょうか。あそこなら、橘さんも戻ったらすぐ来れるでしょうから」
*
就業支援を受けたデミ種たちが調理するこの食堂は、安くバラエティ豊かなメニューばかりで人気がある。
地域のミニコミ誌に取り上げられた先週は、幻界風料理を食べてみたいと一般客が押し寄せて、ひどい混みようだった。
広いフロアなのに、今日もやはり混雑していたが、なんとか二人分の座席は確保できた。
小夜子は、セルフサービスのランチと、理人のためのレモンティーをトレイに載せ、運んできた。
「どうぞ」
「ありがとうございます」
仕事が楽しい。
理人は、『幻界産香草を使ったトマトソースがけ唐揚げ定食』を食べている小夜子に、そう話して聞かせた。
支援課で紹介してもらった郷土博物館で、雑用を手伝っていること。
お掃除の女性が、毎日飴をくれること。
空調が寒くて、ときどき震えていること。
今まで転々としてきた国々では、仕事などせずに昼過ぎまで寝て過ごしていたために、朝起きるのが辛いこと。
でも、朝の空気は澄んでいて、時山の歴史は興味深いということ……。
小夜子はその一つ一つに大袈裟なくらい頷き、笑い、相槌を打った。
「特に燈籠町は、伝統のある素敵な町です。しばらく私が暮らしていたイタリアにも、水路や運河が張りめぐらされた街がありました。私はそこが好きでした」
「ヴェネチアかしら。あちらよりもこじんまりとはしていますけど」
「燈籠町の燈籠は夜、灯りをともしますね。行ったことがありますか?」
「ええ、秋口のお祭りは、とくに綺麗ですよ。みんなで鬼灯の形をした提灯を持って、燈篭の通りを練り歩くんです。水路沿いには屋台がたくさん並んで、田生瀬川には屋形船も出ます。小さな頃から何度も行っているわ、大好きな夜祭です」
「素敵ですね」
理人がため息をつくように言った。
小夜子の顔にぱっと花が咲く。
「今年のお祭り、ご一緒しましょうか?」
誘ってから、図々しいことを言ってしまった、と口をつぐむ。
数秒もないはずが、小夜子にはとてつもなく長い時間に感じられた。
「ぜひお願いします、ええと……すみません、名前が」
「土岐小夜子です。うちの課に土岐という苗字は多いので、小夜子と呼んでください」
「小夜子さん。お祭り、楽しみにしています」
理人が微笑んで言い、彼女の口許がやっとほころぶ。
理人は、市役所の花壇に咲いていた晴々しい朱色の花を彼女に重ね見た。
*
「……あまり、見ないでください」
小夜子はスープボウルに口をつけてコンソメスープをすすりながら、上目遣いで理人へ告げた。
「美味しそうに食べますね小夜子さん」
「あら、やっぱりお腹空いていたんですか?」
「いいえ、全く。なぜ美味しそうに見えるのでしょうね」
彼は目を細くして笑う。
小夜子はスープボウルを静かに置くと、最後の一つの唐揚げにフォークを刺して、トマトソースを絡めた。
「理人さんの一番美味しいと思う食べ物は何です?」
「内緒です」
理人は唇に人差し指を当てて言った。
ヴァンパイアの一番美味しいと思うもの。
ヴァンパイアが市民権を得ても監察下に置かれる理由。
小夜子はハッとして、一旦フォークを置いた。
「……変な質問してごめんなさい」
「責めてはいません。しかし、ずっとわからないことがあります」
彼は両手で頬杖をついて続けた。
「貴女は唐揚げを食べます。それは鶏ですか?それにも命がありますね。なぜ食べて良いのでしょうか」
小夜子は、その問いが導く思考に少し警戒しながら、慎重に言葉を選んで答える。
「わたしたち人は、命を食べなければ生きていけません。ですから、食べるために命を育てます。
この鶏も、このほうれん草も、じゃがいもも、コンソメスープに入っている豚も、人が育てました。狩りや漁をするときにも、全部を取り尽くしたりはしません。
……どんな命でも好きなだけ食べて良い、と考えているわけではない、ということです」
小夜子は理人を見据えたまま、再びフォークを手にとって、唐揚げをぶすりと刺し、それをゆっくりと口に運んだ。
噛み付くと、油がじわっと滲み出る。齧りとられた唐揚げの断面は白い。そこへ彼女はトマトソースを絡めるようにしてから、また口へ入れる。
唇についてしまった赤いソースを、わずかに覗いた舌が舐めとった。
「食べて良い命と、食べてはいけない命がある……それが貴女の答えですか」
「答えが出ているわけではありません、まだ模索しています」
「モサク?」
「探している、という意味です」
「そうですか」
「そして、もうひとつ」
小夜子は続けた。
「……これらの命は、人と話すことができません」
理人はしばらく黙って、黙々と食事を再開した小夜子を見つめた。
やがて理人は、それはとても大事なことですねとだけ言った。
二人の会話はそこで途切れる。
15分後に橘が、身ぶりも大げさに詫びつつやってくるまで、二人が目線を合わせることはなかった。